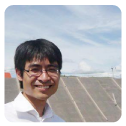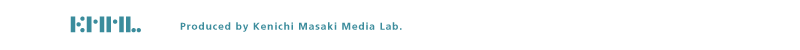ホームレスたちのディナー
街にはクリスマスの雰囲気が漂っている。クリスマス・ツリーにはイルミネーションがデコレートされている。デパートメント・ストアにはトナカイや赤い長靴を象った楽しげな飾りが取り付けてあって、来客の目を楽しませている。スーパーマーケットに行けば、クリスマス・ソングが際限なく流れている。比較的新しいものから、トラディショナルなものまで、クリスマスと名のつくものならどんなものでもそのプレイ・リストには並んでいるようだ。例えば、「Wham!」の「Last Christmas」を耳にしたこともある。日本だけではなく、イギリスでも未だに流れているのかと思って聞いていたら、次にかかったのは「Band Aid」の「Do they know it’s Christmas?」だった。どちらも1984年の曲だ。「赤鼻のトナカイ」が流れたのはその直後だった。
私はホームレスという存在に別段の偏見を持っているつもりはないけれど、彼らを目にすると、ホームレスがいる、ということにはやはり気付く。クリスマスのような華やいだ季節の中にあって、彼らの存在はひと際、印象深くなる。私の目からすれば、ホームレスは、ホームレスではない人と比べて少し違って見える。何が違うのだろうかと考える。おそらく、座っている場所や服装がそのシンボルになっている可能性は高い。彼らはこの寒い冬のイギリスで、どのように夜を生き延びているのだろうとふと考える。今の私にとって、ホームレスはあまりにも遠い世界の人々で、コンタクトをとるような機会はまずない。
街を歩いていると、お酒を飲み過ぎて地面に伏している人を見ることがある。駅に近い大型ショッピングモールの傍にあるカジノ店の脇には、しばしば冷たい地面にビニル・シートを敷いて座っている男性が、硬貨を恵んでほしいと声をかけてくることがある。道ゆく人に煙草を恵んでもらい、ささやかな笑みを浮かべた、それらしき人を見かけたこともある。私の住む街はそれほど大きくないし、治安も悪くない。ホームレスを見かける機会など多い訳ではない。彼らは表立つような場所を歩いている訳ではないが、それでも注意深く街を見ていると、ふと出くわすことがある。「ビッグ・イシュー」誌を右手で掲げながら寂しそうに立ち尽くしているところを駅に近いバス停の横で見ることもある。彼らは、どのように食べものを手に入れ、どのような場所で眠っているのだろう。そんなことをふと考えて、しばらくしてすっかり忘れる。
私が、そのホームレスと話をするという風変わりな機会に恵まれたのは、ある曇空の日であった。その男はポールだと自身を名乗った。イギリス人でその人がポールだといえば、私にはポール・マッカートニーかポール・ウェラーくらいしか咄嗟には思い浮かばない。ミュジーシシャンに限らなかったとしても、次に出てくるのはポール・スミスぐらいがせいぜいだ。しかし、私の眼前にいたポールさんはそのいずれでもなく、目の青い痩せた中年の男性だった。
そこは教会だった。イギリス人女子学生と教会のスタッフが企画したイベントに私は参加していたのだった。「ホームレスにクリスマス・ディナーを!」という名のその企画は、ほとんど全てをボランティア・メンバーが運営しているようだった。事前に告知してあった時間にホームレスが教会を訪れる。彼らにクリスマス・ディナーを提供するという試みである。会場には40名ほどのためのテーブルが用意されていた。各席の中央には「親愛なるお客様へ」と書かれたクリスマス・カードが置かれ、その下に、その日に供されるメニューが敷かれていた。それによれば、暖かい野菜のスープがはじめに用意され、次にメインの肉料理が配膳されるのだと書かれていた。いくつかの料理が一つのプレートに並べられた「Trimmings」と呼ばれるタイプのものだ。ベジタリアン・ソーセージもあります、とある。デザートにはカスタード・プディングを期待することができた。それらを当日集まった私たちのようなボランティア・メンバーが配膳するとのことであった。
メニューの左右には、いくつかのナイフとフォーク、そしてスプーンが縦に並び、中央にコース料理の皿が置かれるのを待っていた。赤いテーブル・クロスが敷かれている。クリスマス・ディナーに相応しい申し分のない彩りであった。けれども、それらは、実際に触れてみればすぐに分かる通り、シートはビニル製のごく薄いものだったし、カトラリー・セットもプラスティックでできていた。そこには、十分に予算のない中で精一杯のもてなしをする、というメッセージが目一杯まで投影されているようで、心にずしりと何かが響くような気分だった。
客が訪れる前にちょっとしたブリーフィング・セッションが行われた。オーガナイザーの一人である教会の責任者が前に出て話をしている。ホームレスの人々をホームレスの人だと思って接することだけは、どうかやめて下さいね。彼らは、多くの場合、精神的な困難を背負っていたり、アルコールや薬物依存症を患っていたりします。おかしなことを言われることもあるかもしれません。特に若い女性の皆さんは「結婚しようぜ」と言われたりすることもあるでしょう。そんなときは「そうですね、ははは」と、うまくごまかしてくださいね。
そこに参加していたボランティアの90パーセント近くは女子大生だった。そこに暑苦しい風貌の私と、クールでハンサムな男子学生が二人くらいいた。人生を通して、私はなぜか期せずして女性が多く集まる場所に座っていることが多いのだが、この日も女性ばかりが集まるイベントであった。
しかし、たしかに、ものごとは理性的に考えられるべきだ。ホームレスたちが客としてテーブルについて、さあこれからディナーだぞというときに、若くて愛らしい女子学生が笑顔で料理を運んできたら心も華やいだものになるだろうと思う。彼女らはサンタクロースの帽子を被って笑顔でやってくるのだ。クリスマス・ディナーは誰にとっても心躍るものでなくてはならない。隣の連中は素敵な女子学生に配膳してもらっているのに、どうして俺だけにこの暑苦しい野郎を割り当てられているんだ?という怒りにも似た疑問を抱かせるには十分な状況にあった。ただし、私にも意見を言わせてもらえるならば、彼らは料金を支払っている訳ではないのだから、そんなクレームなど、知ったことか、ということになる。
実際、ポールさんに料理を運んだのは私だった。20人以上のホームレスが会場を訪れていたが、ポールさんは私の担当する場所に腰掛けてしまったのだ。
ポールさんは終始、そんな不運に不平を言うことなく、食事をしていた。最初は不機嫌そうに食べていたが、私が興味深い顔で彼の隣の席に腰掛けると、嬉しそうに話かけてきた。どこから来たんだい?と尋ねられたので、日本ですと答える。すると日本のどこだい?と質問が続く。日本語のあいさつを知ってるぞ。「サヨナラ」だろ? 俺はいくつかの言語を知ってるんだ。フランス語にロシア語、それにドイツ語もな。あいさつだけだが……。
以前はプログラマーとして仕事をしていたんだけどな、……、と身上について話を始めたかと思うと、彼は目の前に置いてあったキャンディーに興味を示し始め、その話は聞けずじまいになった。学校では何を勉強しているんだ?と尋ねられ、自分のことを答えると、そいつはクールだな、がんばっておくれ、と励まされた。英語に苦労してるんですよ、と話をすると同情してくれた。たしかに外国語ってのは難しいもんだよな。
彼がメイン料理を食べ終わり、僕が皿を下げると、なにを間違ったか、別の学生が再び、同じメイン料理が盛りつけられた皿を運んできた。今度は女性だった。ポールさんは、どうもありがとうと言って、何事もなかったように同じメイン料理の二皿目を食べ始めた。女子学生に悪い気をさせてはいけない、という配慮というよりは、単に食い意地を張っているだけのようだったが、彼のいたずらっぽい表情を湛えた顔は憎めないものであった。しかし、その後にデザートとして供されたカスタード・プディングを彼が口にすると、「うっ、こいつはまずいっ」と小声で叫び、その後一切、手をつけなかったことも印象深かった。きっと味に、小うるさい男なのだろう。
生まれて初めて、ホームレスと面と向かって話をした。そんな機会が外国の地で得られるとは思っていなかった。そんな事情もあって、話が進む合間に、人生の深い教訓か何かをそれなりに得られるのかも知れない、などと迂闊な期待をしていたが、そういった内容の話はついぞ耳にしなかった。日本車といえばだな、あの車が俺は好きなんだ、とか、そこのネーちゃんきれいやね、とかそういう話だった。ただし、ジュースをグラスに注いだり(アルコールは提供されなかった)、皿を運んだりといった私の細かい作業の一つ一つに、彼は謝意を示したのだった。今思い返すと、我々の業務は、レストランの給仕というよりはキャバクラの接客というほうが、言葉の定義上は近かったような気がする。見ず知らずの人に個人的な話をしてそれなりに盛り上がっているのだ。かなり風変わりなものではあったが。客も客なら、‘キャバ嬢’ だって負けていない。なにしろ私がやっているくらいなのだ。
でも、私にはそうした馬鹿馬鹿しい話が心に残った。特別でない人が、特別でない話をするというごく当たり前のことに安心した。壮絶な人生経験や、含蓄に富んだ話よりもずっと現実的だ。ユーモアのセンスと茶目っ気をたっぷりに具えたポールさんが、どういう訳でホームレスになったのか。私はそれを彼に問うようなことは勿論しなかった。そんなことは、私には今さらどうでもいいことのように思えた。一方のポールさんは、いつの日か、例えば来年の今くらいの時期にでも、2013年のクリスマス・ディナーには暑苦しい日本人の男が横に座っていた、と思い出すことがあるのだろうか。きっと思い出さないだろう。それでいいと思う。そして、もし彼に運が向いていれば、来年はこのようなイベントには参加しなくて済むかもしれない。それなら、もっといいと思う。そのころにもきっと「Wham!」が「Last Christmas」を再びスーパーマーケットで歌っているはずだ。
「ホームレスにクリスマス・ディナーを!」は食後のコーヒーを客に出した後、静かに閉幕し、ポールさんと私は握手をし、そして別れた。もう二度と会うこともないだろうと思って、強く手を握った。
▼Vol.012の原稿が届きました!いよいよクリスマスシーズン到来ですね。みなさんは、どんなクリスマスを過ごす予定ですか?