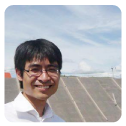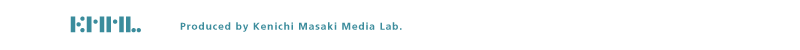ペンギン・カフェ・オーケストラと一組の親子
年末にコンサートに出かけた。こんなに寒くて雨の多い時期に、私の目の前で素敵な演奏をしてくれたのはペンギン・カフェ・オーケストラというグループだった。近年の若い世代の人気ポップ・グループというタイプのものではなく、1970年代の前半あたりから活動しているそうだ。リーダーであったサイモン・ジェフズという人物はもうすでに他界している。それも90年代に。現在は彼の息子さんであるアーサーさんがとり仕切っているそうだ。私はその辺りについてあまり詳しくはないのだけれど、世代を跨いで息の長い活動をしているらしい。厳密にいうと、以前のグループは「ペンギン・カフェ・オーケストラ」と言うが、現在は「ペンギン・カフェ」と言って、別の組織であると書く記事もあった。メンバーもほとんど入れ替わって、私が興味を持っていた、「ペンギン・カフェ・オーケストラ」とはずいぶん違っているという記事を読んだこともある。でも、そのあたりのことは、私にはまだよく分からない。
ペンギン・カフェ・オーケストラの音楽は「環境音楽」とか「アンビエント・ミュージック」とかいうジャンルに組み込まれることがある。このジャンルを「発明」したブライアン・イーノという音楽家が彼らのデビュー・アルバムのプロデューサーだったことが影響しているのかもしれない。でも、ブライアン・イーノの「環境音楽」というと(私は、彼の音楽にとても感心するけれど)一般的にいって、もっとずっと退屈な感じがするのに対し、ペンギン・カフェ・オーケストラの音楽はもうちょっと大衆的である。ブライアン・イーノの音楽は、理解する、というのか、心に滲みてくるのにいささか時間を要する。一度、その面白さに気付くとけっこう病み付きになってしまうような怖さのある音楽を彼は創りだす。一方でペンギン・カフェ・オーケストラの音楽はもう少し軽い。初めて聴いて、十分に楽しむことができるような快活さがある。踊りだしたくなるような軽快さがある。それを以て芸術的価値が低いと言いたい訳ではもちろんなく、いまでも彼らの音楽はそれなりに評価が高いし、私もそういうところが気にいって、わざわざコンサートのチケットを予約したのだった。
コンサートは、フォーク・ミュージックを専門に取り扱うセシル・シャープ・ハウスというロンドン市内の会場で開催された。それはこじんまりした礼拝堂のような場所で、客は200人くらいしかいなかった。そもそもそれくらいしか客席が用意されていないのだから、もともと小さなコンサートなのだ。そしてそれはカジュアルな雰囲気のあるものだった。客層は、老夫婦みたいな人たちから、音楽マニア風の中年男性、若い世代のカップルや子連れの夫婦、というふうに年齢でそのグループを特定できる訳ではなかった。それに混ざって、右も左も分からずおどおどした小心者の私が前から二列目に座っていた。
‘Perpetuum Mobile’ という曲でコンサートは幕を開けた。演奏者は全部で10人いた。ピアノとか幾種類かのパーカッションとか、ウクレレとか、バイオリンとか、オルガンとか、チェロとか、コントラバスとか、いろいろな楽器を駆使して演奏は行われた。いわゆるクラシック音楽のオーケストラがとるスタイルではなく、一般的なポップ・グループがとる編成でもない。ワールド・ミュージックの比較的大きめのグループが紡ぎだす分厚い音を生み出すような編成である。鍵盤ハーモニカも使っていたし、名前のよく分からない民族楽器もいくつか使用されていた。「これは父の音楽です」といった具合にリーダーのアーサー・ジェフズさんが簡単に曲の説明をしたり冗談を言ったりして、コンサートは進んでいく。静かな曲からテンポのいい曲まで、幅は広い。
演奏はとてもエキサイティングなものだった。予想以上に楽しむことができた。けれども、正直なことを言えば、私は客席で起きていたとても興味深いシーンに釘付けになってしまい、演奏よりもそちらに気を取られがちになってしまっていた。
幼い子どもを連れた母親が最前列に座っていた。子どもは5歳くらいで、白人の可愛らしい女の子だった。始まる前からその娘は演奏が楽しみでたまらなかったのか、嬉しそうにはしゃぎまくっていた。そこら中を走り回っていた。演奏は始まっていないしミュージシャンはまだ来てさえいないのだから、それは微笑ましい光景でもあった。でも、演奏が始まってもこの調子だと、うるさくて困るなあと私は内心は思っていた。今度は舞台に並んだ楽器をしげしげと眺め、その辺りをうろちょろし始めた。この調子だと、楽器をいじり始めて、何かの拍子で楽器が致命的に破壊され、コンサートが中止になったらいやだなあ、と私は内心思い始めていた。そして、そのあと娘はいよいよ疲れてきたのか、母親の膝の上で眠りそうになった。この調子だと肝心の演奏中に眠ってしまい、コンサートが楽しめないんじゃないか、と内心彼女が心配になってきた。でも、そんなことは私の知ったことではない。見ず知らずの子どもの心配など、私はここではする義務などない。
演奏が始まると、その娘は緩やかな曲調のときは母親の膝の上で静かに観ていた。しかし、曲調のテンポが速くなってくると、娘は感情をコントロールできなくなってくる。彼女は、母親の膝を飛び降り、そして激しく全身で踊りだした。それは本当に心の底から音楽を楽しみ、自然に体が動きだすのに従っているだけ、という表情だった。とても幸福そうだった。グループと客席の間は2メートル程しかなかったが、そこで娘はエモーショナルに踊り始めたのだった。
私は、母親はどうするのだろうと興味深く眺めていた。親なら、それを取り押さえて席に連れ戻すのだろうか。子どもは無我夢中に踊り狂っている。その母親は立ち上がった。すぐさま娘の腕を掴んだかと思うと、客のいないステージの左側の小さなスペースへ急ぎ足で連れて行った。そして、私は驚いた。一緒になって二人で再び全身で踊り始めたのだ。音楽に合わせ、散々踊って、子どもが疲れたら席に戻る。ミュージシャンたちも嬉しそうにそれを目で追っていた。微笑ましい光景に見えた。踊ったり、席に戻ったりを繰り返した。ときには母親が、さあおいで、と言わんばかりに舞台の横に娘を連れて行こうとする場面さえあった。よく周りを見回すと、他の観客の中にもユニークな人たちがいた。その父親は与えられた席に座らず、子どもを抱きかかえて床に座って一緒にリズムをとっている。そこにはピースフルな雰囲気が漂っているように見えた。
このとき、不意に私は、もう何年も前に乗船したフェリーでの光景を思い出した。
大学を出てしばらくした頃、フェリーを使ってある国内に浮かぶ小さな島を訪れたことがあった。当時交際していたガールフレンドが横にいた。私たちは、帰りにもフェリーを利用する予定だった。しかし、前夜の嵐で予約してあった便はあいにく欠航になった。その日出航する予定の便は軒並み欠航していた。帰りの便を待つ客で、乗り場はひどく混雑した。かなりの時間を待ち、東京に戻る大型フェリーがようやくやってきた。待ちくたびれた大勢の客がそれに乗り込んだ。船内はその島に到着する以前から乗っている客も含めると膨大な人数で、一人一人に座席が与えられるはずもなく、多くの客は床に窮屈そうに座っているような有様だった。日本人も外国人もごちゃまぜに乗り込んでいた。
しかし、しばらくすると興味深いことが起きた。ある西洋人がアコースティック・ギターを鞄から取り出したのだ。大勢の日本人が狭い空間に遠慮しながら座っている中、その若い白人男性は呑気に演奏を始めた。すると、他の場所にいた白人たちが大勢そこに集まってきた。若いカップルや子どもやその親たちが集合し、そこには、あっという間に、外国人のコミュニティが生まれた。大合唱を始めたりしていた。それを怪訝な目で眺める日本人たち。そこには日本人たちの、他人に迷惑をかけてはいけないという暗黙のルールを破った者に向けられる冷たい視線があった。けれども、いくら日本人でも、幼い子どもたちは楽しそうに歌っている西洋人たちのことが、羨ましくて仕方がない様子で、子どもたちはときおり、その輪に近づいたりしていた。おい、君も輪に入りなよとギターを持った男が日本人の小さな男の子に声をかけ、彼はすぐにその周囲にいた子どもたちと仲良くなって、歌い始めた。おい、こら、とその子の親は息子を連れ戻そうとしたが、楽しそうな子どもの様子を見て、そっとしておこうと思ったのか、ひとり元いた場所に戻っていった。遠慮がちに小さくなって子どもの帰りを待つその父親の姿は少し不憫にさえ見えた。周囲では、スタンダード・ナンバーの大合唱がピークを迎えていた。
正直に書けば、私も私のガールフレンドも、その少し離れた狭い場所で、やはり小さくなって座っていた。辛い姿勢を続けながら、その様子を二人で眺めていた。「外国人の彼らの価値観は、せっかくだから精一杯楽しめばいいという姿勢が基本にあるようね。日本人の私たちからすれば、どうにかして他人に迷惑をかけないようにしなきゃと思っているのにね。文化の違いかもしれないけれど、大きな違いね」。真横にいたガールフレンドは笑みを浮かべながら、実にまっとうなことを私に呟いた。私も同様にそう思った。
ふと、そんなずいぶん昔のことを思い出した。
フェリーでの出来事と、コンサート会場で起きたことが、厳密にいって、なんらかの関連性を持っているのかどうかは、ちょっと分からない。けれども、私には、その根底に何か共通した価値意識のようなものが流れているような気もする。それは日本人が、という表現が言い過ぎならば、少なくとも「私たち」が否定しているもの、或いは、発想として持っていないものかもしれない。少なくとも私にはとても興味深かった。それでも、フェリーの中で、外国人の中に果敢に入っていったあの子どもを見て、その親がそれを止めなかったことにも、私には十分に納得できる。
その日のペンギン・カフェ・オーケストラは、子どもを夢中になって踊らせる音楽的な価値を十分に持っていた。そして、その娘の衝動を母親は止めなかった。おそらくこの娘が分別のある大人になって、子を持ったとして、その子がコンサート会場で踊りだしても、やはりそれを止めないだろう。たぶん。
私は何らかの固定化した価値観をここで提示したい訳ではない。けれども、このように私自身を知らず知らずのうちに支配していた価値観の枠組みから、易々と解き放たれた行為を見て、なぜか清々しさを覚えた。それはただ、物珍しさから覚える興味だとシンプルに言うには足りないような気もする。私の琴線に触れるような、もっと特別な何かだったように思う。
最後の曲はアーサー・ジェフズさんのピアノの独奏だった。それはとてもしんみりした曲で、誰も踊りだしたりはしなかった。
▼メリークリスマス☆Vol.013が届きました!いよいよ今年も残り僅かですね。