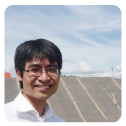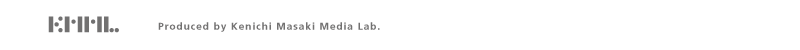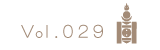

ウランバートルの典型的なバス停
バスで宇宙へ行くための壮大な試み
旧正月の二日目は2月12日だった。僕は自宅に招待してくれた学生の家を訪れるためにバスを待っていた。モンゴルには旧正月に客を自宅に招いて酒や伝統料理を振る舞う古い習慣がある。デールと呼ばれる伝統衣装を身に付け、自動車に乗り、或いはバスに乗って移動する。僕が待っていたそのバス停はイフ・トイローという通り沿いにあって、そこは割に交通量が多い。そのお陰か、様々な行き先を掲げたバスが次々にやってくる。僕の乗るバスは、ウリヤスタイ・デンジンと書かれているはずだが、しかし、それはしばらく待っていも一向に来なかった。
コートのポケットに手を突っ込み、マフラーの中に顎と口をすっかり埋(うず)めてバスを待つ。じっとしているのは寒い。昼間だとはいえ気温は低い。鼻もマフラーの中に隠してしまえたらといつも思う。それができないのは、そうすると途端に眼鏡が曇り始めるからだ。鼻から出た息が行き先をマフラーに遮られて、上側に放出される。それで眼鏡が曇る。眼鏡が曇ると、その無数の小さな水滴は外気の冷たさによって急激に冷却され、凍結する。そうなるとレンズがすりガラスのようになって、途端に前が見えなくなる。それを知っているので、マフラーで覆うのは口の高さまでと決めている。眼鏡をかけない人にはどうでもいいような話かもしれない。
そこに、みすぼらしい格好をした男が一人でふらふらとバス停にやってきた。その男は僕を一瞥し、力なくも、ニヤリとした。嫌な予感がした。話しかけられたら厄介だなと思ったのだ。その表情は明らかに酒に酔っていた。足取りは、かわいそうなくらい歩幅が狭く、向かい風が少しでも吹けば、行く先が変わってしまうほど弱々しいものであった。恐らくこの手の男は黒いジャンパーを着ているものだが、案の定、彼も薄汚れた黒いジャンパーを着ていた。色の褪せてしまった青いジーンズを履いていたが、それはずいぶん下のほうにずり落ちていて、おそらくジャンパーの丈がもう少し短かったら、バス停のような場所では決して見せてはならない物が見えてしまっていたに違いない。
どういう訳か僕はモンゴルに住むようになって酔っぱらった男に声をかけられることが多い。背の高くて喧嘩の強そうなチンピラたちに声をかけられることは、幸いにしてほとんどないのだけれど、刺すような酒の臭いを漂わせた人々が定期的に声をかけてくれる。ほとんどの場合、呂律(ろれつ)が回らなくなる直前のような男たちばかりだ。理由は分からない。酔った男たちにとって、僕の顔は、ついつい話しかけたくなるような魅力があるのだろうか。そんな魅力なら今すぐ捨て去ってしまいたいところだが、それができない。眼鏡がいけないのだろうか。そうだとしたら、眼鏡のせいで、僕はずいぶん損をしていることになる。素面(しらふ)のもっと若くて美しい女性たちが、思わず声をかけてみたくなるような顔でありたいのだが。
薄汚れたジャンパーの男は、おもむろに僕に接近し、予想通り、話しかけてきた。彼の目を見ないようにしていたが、そのような行為は無駄であった。そして彼は、そのまま本題に入るような唐突な話し方で僕に問うた。
「宇宙へ行くには、どのバスに乗ったらいいんだい。」
詩人のようなその問いかけに僕は驚いた。いや、正直に言えば、驚かなかった。ただ、滑稽にみえただけだ。その男には凡そ不釣り合いなその質問に吹き出しそうになったのだ。本当のことを書くと、ウランバートルの中心地にサンサルという地域がある。サンサルは地名だが、それとは別に「宇宙」の意味を持つ単語だ。彼はサンサル地区へはどのバスで行けばいいのかと、しどろもどろにも、まともな質問をしただけなのだった。だから、それに吹き出すのは筋として間違っている。
しかし、そのとき僕は、彼は本当に宇宙に行きたいのだと信じてみたかっただけなのだ。彼が千鳥足のまま、冷凍庫のように冷えきったローカル・バスに乗って宇宙に行けたなら、それ以上におめでたい話はない。むしろ僕は、彼にはぜひ、この旧正月休みのうちに宇宙に行って頂きたいとさえ思った。
いくら暇だからといって、そのような空想を頭に描いていることが他の人に知れるのは恥ずかしいことである。そういう事情もあって、彼に対してまともな受け答えをするべきだと我に返った。でも、そのバス停からサンサル地区を訪れたことのない僕には正直に、分かりませんとしか答えられなかった。男は「ちぇっ」と言って、他のモンゴル人に声をかけるために僕の目の前を後にした。けれども、そのような酔った男をまともに相手にするモンゴル人は僕を最後についぞ現れなかった。
民営の小型マイクロバスが、バス停に停車し、案内人が行き先を告げていた。うちひしがれたように、そして、最後の救いの縄をたぐるような表情で、その男はマイクロバスに再び尋ねた。「宇宙に行きたい……。」しかし、案内人も同様に冷徹だった。「行かないよ」。このようなやりとりは、次のマイクロバスが到着したときにも同様に行われた。マイクロバスの案内人は、泥酔客を乗車させないよう注意深く観察しているようだった。そのみすぼらしい男は、極めて哀れであった。
男は新たな作戦を考えていた。このままでは、バスには乗れない。彼は次のマイクロバスが来ると、行き先を案内人に尋ねることなく、つまり、そうすれば、泥酔していることを知られる可能性が少し低くなる訳だが、バスに無言で乗り込もうとした。彼にとって、宇宙へ行くことは、もはや第一の目的ではなく、バスに乗ることに大きな意味を見いだしているかのようだった。バスに乗らなければ、壮大な彼の物語は始まりさえしないのだと言い聞かせるような姿だった。
しかし、その周到な作戦は失敗に終わった。乗り込もうとした際に、デッキから足を踏み外し、体ごと道路に落ちてしまったのだ。そして、それは二重に哀れに映った。
ちょうどそこに、僕が乗るはずのウリヤスタイ・デンジン行きと書かれたバスが到着し、僕はそのみすぼらしい男の行く末を案じながら、後ろ髪を引かれるような思いで乗車した。彼はマイクロバスに乗れたのだろうか。案内人に再び追い払われたのではないだろうか。「宇宙に行きたい……。」彼の力のない声が僕の脳裏にこだましていた。
しばらくすると僕の乗ったバスが大きく左折し、僕はある残酷な事実を知った。バスが、サンサル地区のバス停に停車したのである。僕は思わず、バスの来た道を振り返った。バスの後部座席の大きな窓は凍り付いていて、そこからは、男の姿どころか、全く何も見えなかった。それは、僕の眼鏡にもよく起きるような凍り付きようだった。デールを身につけた艶やかな女性や男性、そして子どもたちばかりが目につく、華やかな日であった。
▼まるで映画のオープニングのよう☆ 桐山さんの文章は、実に映像的ですね。日常の何気ないやりとりが、現地の臨場感とともに心地よく伝わってきます!それにしても哀れな男、その後が気になります…