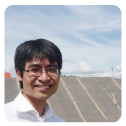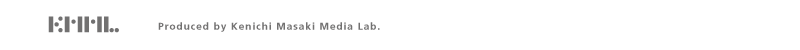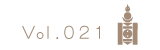
ウランバートル国際マラソン開会式はこのステージで行われた。
第3回ウランバートル国際マラソン
ウランバートルの7月はずっと雨が降り続いている。異常気象を思わせるくらい、来る日も来る日も雨だ。時折太陽が機嫌のいい顔をのぞかせるのだが、すぐに不気味に浮かぶ巨大な雲に隠されてしまう。ねずみ色の濃い雲が次第に街の空全体を覆い、辺りを陰気な景色にすっかり変えてしまう。すると間もなく、ぽつりぽつりと大きな雨粒が落ちてくる。表通りに雨が降ると不意に漂ってくるのが雨の匂いだ。雨の匂いには、いつも、なんともいいようのない気分にさせられる。好きでも嫌いでもない。ただ、懐かしさとか、心細さとか、そういうものを僕の心に運んでくる。どうして雨の匂いはいつも、決まってあんな香りがするのだろう。しかも、モンゴルでも日本でも同じ匂いなのだ。
ウランバートル国際マラソンの当日も雨が降っていた。朝は小雨だったが次第に空が深刻そうな色に変わり、しばらくすると、厄介なほど降ってきた。大勢のランナーが一斉にスタートしたイベントの序盤の頃はまだ良かったのだが、ハーフマラソンの先頭集団がコースの半分を走り終えた頃から、本格的に降ってきた。
僕はその数日前まで、マラソンに出場するのを辞めようと思っていた。マラソンの参加申込みのために70ドルほどの支払いをすませた大会の一ヶ月ほど前に、練習のために20キロ程を軽く走っていたら、急に左足の膝が痛み始めたのだ。もう何年もランニングをしているのだが、このようなことは初めてだった。これ以上痛みが広がるのも危険だなと思い、その日は走るのを辞めた。ちょうど走っていた場所が都市部を離れた草原とゲルの見えるうら寂しいところで、のそのそと家畜の牛が道路を横切っていく。しばらく後を馬が二頭、ぱかぱかと通り過ぎた。どれも深い茶色だった。自動車がそれを避けながら慎重に通り過ぎる。ほんの少し都市部を離れると長閑な風景と退屈にだらりとのびた道路が見えてくる。ほんの十数キロ、都心を離れるとそんな光景になる。それがウランバートルなのだ。僕は途方に暮れてしまったが、はじめのバス停を探しながら何キロかをゆっくり歩き、呼吸を整えたあと、黄色の公共バスに乗った。バスは郊外から都心に向かい、国立教育大学の前で僕を降ろし、また忙しそうにどこかへ走り去った。
数日後、もう治ったかなと思って、再び10キロほど走ってみると、案の定、痛くなる。こないだよりむしろ痛みが強い。しばらく走るのはよそうと思った。この調子だと出場は無理だ。練習もしないで40キロにも及ぶマラソンに挑戦するのは無謀だし、仮に走っても、当日もきっと足が痛くなるだろう。こうして大会二日前まで、支払った70ドルのことはもう考えないことにして、呑気に生活していた。いったん諦めると、そのことをもう考えなくなってしまう性格で、冬期をのぞいてコンスタントに続けていたランニングをきっぱり辞めてしまった。ちなみに70ドルは、モンゴルでは4人くらいでかなり豪勢な食事ができる額である。
ところが、大会が近づくにつれて、出場を予定している周囲の友人たちも、そわそわし始め、君も前日に開催されるパスタ・パーティくらい参加したらどうだい、と勧めてきた。マラソンイベントの前日は、パスタ・パーティというものが開催されることがある。出場者が懇親を深めることができ、さらに炭水化物を前日にたくさん摂取することで当日のランを最適なものにする、というねらいがある。世界中のマラソンイベントでパスタ・パーティが実施されていて、ウランバートル国際マラソンも市内のレストランで開催した。しつこいようだが、70ドルも支払っている訳だし、せっかくだからパスタ・パーティでパスタだけでもたべようじゃないか、ということになった。その権利が僕には立派にあった。
パスタ・パーティは前日の夕刻に始まった。予定開始時刻より40分遅れてスタートした。パーティの司会者は外国人を含む人々を前にして「Sorry, it's Mongolian time!(どうもすみません、モンゴル流の時間感覚ですので!)」と半ば自嘲気味に釈明していた。マラソン出場者に囲まれながら、パスタをお腹いっぱい食べると、なんだかマラソンに参加しなくてはいけないような気がしてきた。よその国から来たと思われる背の低い長髪の青年に「パーティを楽しんでいるかい?」などと聞かれた。日本から、わざわざこの大会に参加するために来たという何人かの人たちにも出会った。翌日の大会に出場するかについて、僕はかすかに迷い始めながら、ビュッフェ・スタイルの会場で熱心にパスタを皿に盛り付けていた。格別においしいパスタだったという訳でもないのに、このような心境の変化は不思議なものだった。よくよく考えてみれば、足が痛くなったら途中で棄権することもできる。無理をしなければいいのではないか。そうした気分が心の中に沸き上がってきたのだった。
翌日、6月2日が大会の日だった。先ほども書いた通り、ウランバートル国際マラソンの当日は雨が降っていた。しかし、なぜか僕はもうマラソンに出場する気になっていた。そして、胸にゼッケンをつけ、ランニング・シューズを履き、ウェアを着て、朝7時にはスフバートル広場に到着していた。途中で棄権しても誰からも叱られるようなことはないのだ(当たり前である)。この日は6月にも関わらずかなり気温も低く、雨もそう簡単にやみそうになかったが、走っていれば気温も気にならなくなるだろうと思った。スタート地点であるスフバートル広場にはすでに多くのモンゴル人や外国人がウォーミングアップを始めようとしていた。
小雨の中での寒いスタートだった。以前、モンゴルの別のレースに参加したときもそうだったのだけれど、スタートの合図がいつあったのか分からなかった。主催者らしき人たちの何人かがモンゴル語や英語で挨拶をしたのを適当に聞き流したあと、すぐにスタートラインに並ばされた。一斉に出場者全員がスタートしたのを見て、僕も慌ててスタートした。国際マラソンという名にしては小規模で300名ほどの出場者である。しかも大半は20キロコース以下のランナーである。10キロとか5キロのコースもある。全速力で走り去る子どもたちを僕は大勢見かけたが、彼らは3キロのコースだったのかもしれない。
足が痛くなる時期が遅くなればそれだけ長い距離を走れるだろうと考えて、かなり遅いペースで走った。できる限り足に負担がかからなければいいだろうと考えていた。それでも後ろには大勢の人が走っている。もちろん、それよりたくさんの人が僕の前を走っていた。ピース・アヴェニューをまっすぐ東に向かって走ると、沿道から大勢の歓声が聞こえた。そこに知っている人などいなくても、なぜか嬉しいものだ。
微かな雨が体を冷やし、走るにはむしろ心地よかった。しばらくするとほとんどのランナーたちは折り返し地点を迎え、辺りを見渡してもランナーが少なくなってきた。この頃になると、都市を離れ、草原とゲルと、点在する小さな一戸建てがみえるだけだ。時折、牛や羊の牧草を食(は)む姿がみえた。空は青白く遠くには霧がかかり、これから天候はどうなってしまうのだろうと考えながら走った。そして目の前にはあきれるほどまっすぐに続く道路が見える。ゆっくり走っているせいで、一緒に走っていた友人もいよいよ先を行き、後ろからくるランナーにも抜かれるようになった。褐色の肌をした、やや太った女性がイヤホンの音楽に合わせて軽快に僕を追い越していくのを目で追っていった。僕に疲労感は全くなかったが、ただ足の痛みが心配だった。そして、実は、残念ながら少し痛みが始まっていた。沿道にはごく稀に仏頂面をした警官が警備に当たっているだけになっていた。こんなときくらい、ちょっとした声援をランナーにかけてあげればいいのにと思ったが、それは我々の仕事ではない、とでも言いたげな表情で、むしろ僕を睨みつけてくることさえあった。でもそんなことは僕にはどうでもよかった。
トール川という大きな川を越え、大きなガソリンスタンドが見えた。病的に太った警官が二人で立っていた。果てしない草原の光景に少し変化が訪れたところだった。僕は足の痛さを少し正確に確かめようと歩くことにした。すると、すかさず、また誰かが僕を追い抜いていった。その辺りでたぶん15キロか16キロくらいは走っていたのではないかと思う。後ろから急に応急救護車が近づいてきた。モンゴル人の運転手がモンゴル語で僕に声をかけてきた。おいおい、疲れたのか?救護車に乗るかい?さあ乗れ! 僕は少し迷った。もう少し走ることはできそうだが、完走することはちょっと無理だと思っていたところだったのだ。左足の膝も少し痛む。なにしろまだ半分も走っていないのだ。雨も次第に強くなってきていた。
ウォーミングアップする選手たち。
モンゴル人運転手は、猟師が獲物を捕らえたときのような表情で車に乗るよう再び促した。彼らの仕事は急病人やリタイヤするランナーを車に乗せて帰ってくるというものだから、与えられた職務を熱心に全うしようとしているのには違いないが、マラソン・ランナーの気持ちを分かっているような人たちではないようだった。特に、参加者のなかでも、後ろのほうをぎりぎりで付いて行こうと頑張っている素人のマラソン・ランナーの気持ちを。ほとんどのランナーにとって “リタイヤしないこと” はどうしても譲ることのできない “誓” のようなものなのだ。リタイヤしないという “誓” を守るために参加費70ドルと、外国人なら渡航費を含めてつぎ込んでいるのである。
けれど、僕にはこのレースに限って言えばそのような大切な “誓” も始めからなかったし、いずれ棄権することが分かっていた。それに、救護車が横にいるうちに棄権しておいたほうが、後になって困ることも少ないかもしれないと思った。いよいよ走ることができなくなって、立ち尽くしていても、すぐに彼らが僕を発見してくれるとは限らない。雨もどんどん酷くなっていったら……。後になって、「どうしてあのとき救護車にのらなかったのだ」と冗談交じりに皮肉を言われるのも癪にさわる。もちろん、今から考えれば、後ろのほうを走っているランナーは、リタイヤを今か今かと待っている救護員たちに四六時中見守られている訳で、そんな心配はほとんど不要だったのだが。
僕は救護車に乗ることにした。その瞬間、僕のマラソンレースは終了してしまった。誰よりも早い、あっけない幕切れだった。もちろん僕はこれまでの人生で、このマラソン以外にも、いろいろなことを諦めてきた訳だが、諦める瞬間というものはどんな場合にしても清々しいものではない。小さな挫折、虚しさ、自分に対する言いようない苛立ち……。リタイヤすることを分かっていて参加していたのに、どうしてこんなことを僕は感じているのだろう。そんなことが頭の中が駆け巡る中、僕は救護車の窓越しにマラソン・コースを眺めていた。こんなことなら、始めから出場などしなければよかったのだ。救護車の中には人工呼吸などの応急処置に使うための道具の一式が備え付けられていて、脱水症状のランナーのための500ミリリットルのミネラルウォーターが2ダース程積んであった。救護車は時折ものすごいスピードでコースを走ったかと思うと急激に速度を落としたりした。相変わらず運転手はランナーたちに向かって「いつでも救護車に乗ってもいいからな」としきりに乗車を勧めている。声をかけられたランナーは、その度に黙って首を横に振った。
しかしこうして、自動車でマラソン・コースを走り抜けてみると、ずいぶんたくさんの人が僕の前を走っていたのだなということに気付く。ランニング・フォームの美しい人、太り過ぎていて今にもひっくり返りそうな人、我慢が顔に滲み出ている人……。一人の南欧系の長い黒髪の女性が走っていた。僕を乗せた救護車は彼女の後ろをしばらくゆっくり走っていた。彼女は黒いタイトなランニングウェアを着ていたが、雨のためにぐっしょり濡れていた。腕の振り方、ペース、ストライド(歩幅)、それらがまるでコンピュータでプログラミングされたように一定している。顔の向きも全く変わらず、おそらく数十メートル先をただ見つめている。きっと様々なレースで経験を積んだ人なのだろうということがすぐに分かる。周囲のランナーが一人、また一人と追い越されているのを見ると、かなり速いペースを維持できているのだろう。彼女の走る表情を見ることはなかったが、後ろ姿は美しかった。こうした安定したフォームを眺めていると見とれてしまうほどだった。救護員の運転手が、僕に声をかけてきた。君は外国人だな?どこから来たんだ?日本人ですと答えると、少しはモンゴル語ができるんだなと言う。ほんの少しだけですよと答えた。しばらく世間話をしていると、運転手はモンゴル語での僕とのやりとりに不便さを感じ始めたらしく、「君、ロシア語はできるかい?」と尋ねてきた。彼はロシア語に自信を持っているようだった。全くできませんと答えると、ひどくがっかりし、そこでぷつりと会話は終わってしまった。性格の明るい軽快なおじさんだったが、それ以上僕が熱心に話すことのできる話題もなかった。僕は黒いランニングウェアの女性を再び眺めることにした。
何人かのランナーがリタイヤして “僕の” 救護車に乗り込んできた。大丈夫ですか?と救助されたランナーに声をかけてみると、ああもう死にそうだといって、ミネラルウォーターをごくごくと飲んでいる。少し頭痛がするというので、酸素の吸入もしていた。そういう人が二人くらいいた。
このようにして、救護車はスフバートル広場に到着し、僕は車から降ろされた。すでに何人かのフルマラソンのランナーがゴールを終えているようだった。左足が少し痛むのを感じた。僕の友人たちはまだゴールしていなかった。まだスタートから3時間ほどしか経過していなかった。僕はしばらくゴール付近を理由もなく歩き回っていたのだが、急に何か恥ずかしいような気分になり、そそくさと家に帰ることにした。友人たちが無事ゴールするとしても、まだしばらく時間が必要だろう。雨宿りをして待つ場所もない。
結局、後になって聞いた話では、出場した友人の中で完走できたのは二人だけだった。5時間という制限時間の短さ、あいにくの悪天候、そして、救護車によるリタイヤへの執拗な誘惑など、いろいろな条件が重なったせいでフルマラソンを完走できたランナーは思いの他少なかったようだ。ウランバートルの標高の高さも多少の影響があったのかもしれない。左足の膝が完治し痛みが出なくなれば、またレースに出場してみたいと思うけれど、それはいつになるのだろう。
連日雨が降ると、時折このマラソンの日の記憶がふと蘇ってくる。忘れ去りたい記憶だという訳でもないが、心地よい記憶という訳でもない。マラソンは確かに過酷な競技である。
▼今回は「桐山さんとマラソン!」という意外な組み合わせです!(失礼)私は高校時代に陸上部だったので、“誓”という感覚がなんとなくわかります。たしかに「マラソンは過酷な競技」です。お疲れさまの桐山さんにメッセージを!ところで、もうすぐオリンピック☆楽しみですね!