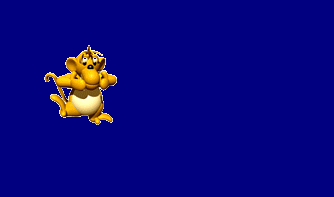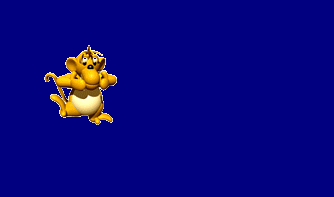
『中年期の危機的移行についての検討』
A類学校教育3年 西村 昭徳
第1章 人生移行とは何か
第1節 生涯発達的研究について
1 本研究の目的
2 生涯発達の意義
3 生涯研究の方法
4 生涯発達研究の歴史
第2節 人生移行と危機
1 「人生移行」の概念
2 危機的移行
第2章 生涯発達過程における中年期
第1節 成人期の移行
1 中年期の特異性とその捉え方
2 成人期の発達課題
第2節 中年の危機
1 「中年の危機」の定義
2 「中年の危機」は存在するのか
第3章 まとめと今後の展望
第1節 現代社会における成人期
第2節 今後の展望
第1章 人生移行とは何か
第1節 生涯発達的研究について
1 本研究の目的
ながびく不況の中で、企業の倒産やリストラが相次ぐ現在の社会状況は、その中心を担う成人世代の心理面にも大きな影響を及ぼしていると考えられる。自殺やうつ病が最も多い世代とともいわれる成人世代とは、どのような特徴があるのか以前から疑問を持っていた。今年の9月に行われた教育実習で、その疑問に拍車をかけるような現役教師の発言を聞いた。「今の学校が求めている教師は、情熱を持った人です。たとえ、どんな職業に就くにしても、情熱的であって欲しいとおもう。」これは、自分よりも若い実習生たちへのはなむけの言葉であった。しかし、現役の教師のほとんどは成人世代に属しているのであり、いつまでも若さを押し通すことはできないと思われる。子どもに対して、若さや情熱を維持し続けることは本当に可能なのかと疑問は大きく膨らんだ。
そこで、本研究では、人間の発達過程における成人期に注目し、特に中年期の危機的状況についての今までの研究と成果について検討してみたい。
2 生涯発達の意義
近年ライフスパン、ライフサイクル、ライフコースといった用語が、しばしば用いられるようになった。ライフスパンという言葉は、生まれてから死ぬまでの時間的隔たり、すなわち、命の長さ、寿命を表している。ライフサイクルという言葉は、生命を持つものの一生の生活にみられる規則的な推移のことで「出生・成長・成熟・老衰・死亡などの生命現象によって規定された一生のコースを生活現象としてとらえたものである。個人のライフサイクルは家族のそれと表裏一体をなしており、家族のライフサイクルを家族周期と呼ぶ。」(盛岡、望月、1991)。つまり、子どもを産む年代とか、子育てを終える年代、老夫婦2人で生活する年代などである。
本来、発達心理学は、受胎から死に至るまでの全生涯に生起する心理学的な問題の研究をすべきにもかかわらず、最近までは、子ども期と青年期に限定されてきた。しかしながら、生涯発達の意義を考えると、発達研究を人生の前期20年に限定することなく、複雑多様に変化する後期60年を加えた全生涯過程の研究が重要になる。それも単に年齢変数を60年追加するという発想ではなく、ライフコースのさまざまな時点で生じる変化の形と特徴を「標準年齢的要因のみならず標準歴史的要因および非標準的要因の影響も考慮に入れて」(Baltes、et al.、1980)、全生涯的視点から明らかにすることである。人生前期は人生後期や全生涯との関係において成立しているのであって、発達研究が生涯的文脈でおこなわれるならば、従来の研究成果に対する見方も変わるし、後期の研究も発展するに違いないと考えられる。
3 生涯研究の方法
発達心理学における生涯的視点に関する方法論的考察には、発達的方法と発達理論の双方を考慮に入れなければならない。このようなアプローチの特徴は、生涯発達心理学の伝統を反映している。この分野の多くの業績は方法論的進歩によって促されてきた。たとえば、心理学的発達を究明するためには縦断的デザインを用い、歴史的変化からくる成分(コホート要因)を個体発生的成分から単離する必要がある、といったことである。方法論および理論への意識的な関心は、生涯研究が発達的学識を極度に拡張することによって生じてきたものである。たとえばそれは、長期にわたる変化や、拡張された因果的関連を扱うことを目指している。その結果、生涯研究者の発達研究の理論的及び方法論的な特徴と、発達的アプローチの必要性および限界を、できる限り明らかにすることを第一義とするようになった。
それでは、生涯発達心理学の理論ないし方法論を最大限に活かすような具体的な研究方法とはなんであろうか。すべての生涯発達研究者は、生涯研究に適合する研究方法を検索している。データ採取という側面での主要な研究方法として、
次のようなものが挙げられる。①実験的方法、②現象学的方法、③質問紙法、④行動観察法、⑤介入法、⑥テスト法(知能テスト)である。
次に、生涯研究法のデータ処理の側面について考える。人間をその発達過程にそって分析するための伝統的な二つの方略として、縦断法と横断法がある。この二つの方法は、かつては多くの研究者が、同一ないし相互交換的な結果をもたらす方略として仮定していたものであるが、この仮定が誤っていることは、今日では、明白となっている。縦断的デザインと横断的デザインとに含まれる一つの本質的に方法論的な論点は、横断法におけるそれぞれの年齢グループは異なる世代に属する人たちであり、それぞれのコホートを代表しているのに対して、縦断法のグループはグループは通常、単一のコホートに属しているという事実と関係がある。縦断方と横断法とがもたらす結果の、相互の食い違い、ないし不一致の発見は、生涯研究にとって思わぬ新しい展開をもたらした。縦断研究と横断研究との知的機能に関する生涯的データの食い違いは、コホート差によるものと解釈されている。(Baltes
& Brim、1984;Schaie、1979)
Schaie(1965)は、横断的アプローチと縦断的アプローチの両方の特徴を活かすとともに、両者の欠点ないし限界を軽減させるための新しい発達研究デザインを提唱した。この新しい方法は彼自身、「系列的デザイン」と呼んでいるもので、近年これの一般的適用性を評価する人によって「一般的発達モデル」とも呼ばれている(Lerner、1976)。この方法を用いることによって、横断・縦断の両アプローチに含まれる交絡を解消させることが可能である。すなわち、両アプローチの手法を合併することによって、年齢・コホート・測定時点の相対的寄与を分離して評価し、グループ間のどんなさが年齢の違いによるものか、またどんな差異がコホートの違いによるものか、あるいはどんな差が測定時点の違いによるものか、を知ることが可能になった。
4 生涯発達研究の歴史
これまでの生涯発達に関する研究の流れを考える。まず、Hall(1904、1922)は、「青年期」と「老年期」を著わしたが、これは、生涯発達的な視点から青年期と老年期を書いたのではなく、生涯発達研究の流れを呼び起こすことにはならなかった。
次に、Buhler(1933、1959)は、「心理学の問題としての人間の生涯」において、初めて人間の一生の発達心理学を構築した。多くの伝記的資料を収集し、人の生命全体という観点からモデルを作り、個人の誕生から死に至るまでの全生涯を5段階にわけた。また、Erikson(1950)は、心理社会的発達の観点からライフサイクルに基づく発達論を構想し、乳児期から老年期までを8段階に分け、「人格発達分化の図式」と呼んだ。同じころに、Havighurst(1948、1953)は、乳幼児期から老年期までの発達段階で要求される発達課題を掲げた。
第62回アメリカ心理学会(1954)において、老年問題が初めて学会で取り上げられて以来、人口の高齢化も伴って、高齢者の研究に対する関心が高まっていった。しかし、中年期、老年期を通じて生涯発達的研究が本格的に行われるようになったのは、Gould(1972、1978)、Levinson(1974、1978)らの成人発達に関する研究をはじめ、1970年代以降である。
従来の発達心理学は、遺伝と環境が子どもの発達に及ぼす影響を研究してきたが、その主たる関心は子どもの身体的・心理的危機や行動の発達に向けられていたことも合って、年齢の効果を問題にして、個人の生活した社会や歴史の要因は、意図的に考慮の外に置いてきた。その一方で、社会学では、個々人の人生は人の生活している社会的機能の変化や社会構造の変動、あるいは特定の歴史的事件の影響を受けるという観点から、年齢要因よりは社会的要因や歴史的要因を重視している。Baltes(1968)、Nesselroadら(1979)は、社会的・歴史的要因としてコホート効果に注目し、特にBaltesは1978年に、年報「生涯発達と行動」を初めて編集した。
日本では、橘(1971)が、大著「老年学」を公にして、老年心理学研究の端緒を開いた。また、正岡ら(1990)は、長期的展望のもとに現代日本人が急激に変動する社会的・歴史的状況の中でいかにライフコースを形成してきたか、また形成しているかについてコホート別の比較研究を行っている。
第2節 人生移行と危機
1 「人生移行」の概念
「人生移行」life transitionとは文字通り人生の移りゆき、すなわち生まれてから死に至るまでの移りゆきのことである。人生の過ごし方は個人差、性差、時代差、文化差があって一概には言えないが、現代日本の平均的な個人を考えると、出生後3~4歳になると保育所・幼稚園、6歳以後は学校教育のシステムに乗って成長していく。高卒あるいは大卒で就職し、多くの人は結婚して自分たちの家族を形成する。子どもを産み育て、教育して、やがて子どもは家を出ていき、親は職業生活から離れる。子の出払った老夫婦の時期は、ふつう年長で寿命の短い男性が先に死亡して人生を終える。
人生移行の中には、入学、卒業、就職、結婚、退職など社会の大多数の人々が経験したり、あるいは社会成員たちがその移行を人生のある特定の時点で経験することを社会全体から期待され、本人もそれを予期している移行と、不治の病気の宣告、愛する人のし、災害など突発的に起こる出来事とがある。一般的に、後者は予期しないだけに本人や周囲の人に与える影響は大きいが、前者のように予期できる移行でも、移行の前と後では大きな変化が生じるので、ある個人にとっては衝撃は大きい。このように人生移行は危機を内包している。
2 危機的移行
Caplan(1961)は、「危機状態の定義」を次のようにしている。「危機状態は、人生の重要な目標に到達するのを妨げられ、障害に直面したとき、一時期、習慣的解決を用いては克服することができない時に発生する状態である。混乱の時期と同様の時期が結果として起こり、その間、解決しようとするさまざまな試みがなされるがうまくいかない。結果的にはある種の順応が、その人やその人の仲間にとって良い結果をもたらすかもしれないし、そうでないかもしれない形で達成される。」。一口で言うならば危機とは「落ちついた状態の転覆」である。人間は生理的にホメオスタシスを求めると同様に、心理的社会的平衡と安定を求める欲求を持っている。その平衡と安定の状態が破れるのが危機である。
「危機的移行」というと個人の人格が崩壊し、破壊へ向かうような危険な状態を考えやすいが、必ずしもそればかりではない。危機は、分かれ目であるから、人生の中で次々と起こる出来事に対して適切に対処すれば人間の成長につながるし、失敗すると破局につながる。このように、危機場面は、発達段階の境界でも起こり、障害と発展の双方の機会になる。
危機的移行の定義としてWapner(1983)は、“人間-環境システムの急激な崩壊”と定義している。人間と環境とは相互に影響し合いながら一つのシステムを形成している。安定していた人間-環境システムが、発達の要因や環境の変化によって均衡が破れ、新しい人間-環境システムを形成しなければならないような移行を危機的移行という。移行が単なる「変化」なのか「危機的移行」なのかを区別するためには、移行の前と移行の後を比較すると明瞭になる。発達的移行にあっては、ある発達段階とそれに続く発達段階の比較、人生の出来事にあっては、その事件が生起する前と後の比較をして、大きな変化があり、移行過程にある人や出来事の渦中にある人が激しいインパクトを受け混乱しているならば、それは単なる変化ではなく危機的移行である。
第2章 生涯発達過程における中年期
第1節 成人期の移行
1 中年期の特異性とその捉え方
成人期に、特に中年期(30代中頃~40代中頃)の移行は独特である。ひとつの時期から別のそれへの移行という捉え方が難しい。確かに、就職、結婚、子どもの誕生、昇進、転職、病気、離婚等々は、中年期に共通あるいは近い項目として捉えることができる。そして、家族心理学も家族社会学も、このポイントから接近する方法論を採ってきた。こうした考え方は、項目が整理された見やすさがあり、便利のように思える。しかし、私たちはこのように項目分けした状態で中年期をすごすのではなく、自分が自分らしく生きることを模索し、それを実行に移す時期となる。だから、主要なポイントは項目ではなく、心理的にどのような状況かについて考える必要がある。つまり、中年期の移行は、時期的移行ばかりに目を捕らわれると、その本質から遠ざかってしまう。
法律上では、わが国は中高年促進特別法(1971)の中で45歳から65歳を中高年者の年齢範囲と定めている。だが、発達心理学では、成人世代の位置づけは一定しておらず、諸家によって異なっている。たとえば、Neugerten(1968)は、人生の時間体験の感覚から中年期を位置づけている。つまり、青年期、成人前期頃では未来は限りなく広がっていると思いがちである。だが、人生の後半頃にさしかかると時間展望の再構成が行われる。そして人生は誕生からの時間よりも生きるべき残された時間から測定され、未来の自己、これからの人生や死を今までと違ったようにみるようになるのが中年期の始まりであるといわれている。
2 成人期の発達課題
Jung(1960)は、パーソナリティの生涯発達で中年期を重要視した最初の人であった。これは彼自身が彼の中年期において激しい危機を体験したことが基盤となっている。彼は40歳を人生の正午と呼び、人生の後半期が始まるとした。中年期の発達課題は、若さや能力の減少を受け入れ、自分の人生や目標を振り返って再検討ことである。つまり自分の人生を正しく見直し、外的生活から内面的生活に重きを置くことになる。
Buhler(1961)は、成長-頂点-低下の生物学的曲線に対応したパーソナリティ発達の過程を述べている。成人前期(25~45-50歳)では、人は、職業、結婚、家族を実現させ、安定した適応をするために発展することが目標である。成人後期(45~50-65~70歳)では、これまでの人生の目標を自ら再評価することが目標であると述べている。
Erikson(1959)は、自我機能の社会・心理学的発達を8つに区分して展開させている。各段階には各々の発達課題があり、各々の課題を達成し、次の段階へと進むときに心理・社会的な危機を通り、それを乗り越えられたときには生きていく上で大切な力が身にそなわる。
Havighurst(1972)は役割理論を基礎として生涯を6段階に分類し、各時期の具体的な課題を設定している。成人前期(18~35歳)の課題は、結婚相手と生活することを学ぶ、家庭を作る、子どもを産む、家を管理する、地位を確立する、市民としての責任をもつ、気のあった社会的仲間を見つけることが課題である。
以上のように、各研究者の立場によって中年期の位置づけは多少異なるが、大体において成人期はこれまで生きてきた前半の人生を振り返って再評価し、次の世代への橋渡し役として人生の後半期に新たに再出発することが課題といえる。
第2節 中年の危機
1 「中年の危機」の定義
「中年の危機(mid-life crisis)」ということばを最初にもちいたのはJaq-uesであった。彼は、芸術家の創造性が40歳前後で変質することを指してこのことばをもちいた。つまり、ここでいう中年の危機とは、個人の内的な発達変化を示すことばであった。しかし、近年、心理学や精神医学の分野で用いられる「中年の危機」とは、青年期と老年期の間の中年期というライフサイクル上の時期に人々がさまざまな出来事にであったときの、ある種の選択を迫られるような状況とそれへの対処行動を指すことばである。しかも、ここでいう危機的状況とは、決して特殊な出来事や体験を指すのではなく、中年期というこの時期に誰でも体験する可能性のある標準的な危機(normative crisis)をいう。
Levinson(1978)は、中年の危機を人生半ばの過渡期と呼び、40歳から45歳の成人の80%がこの意味で危機を体験していると述べている。また、精神分析の観点から中年の危機に着目したのがGould(1978)である。彼は、30代から40代半ばの時期は、社会生活において大きな変動を経験し、自分自身への懐疑や目標到達への焦燥という危機を経験するという。しかし、40代半ば以降は、根拠のない期待を捨て去り、真の自己の受容と円熟に向かうようになる。
2 「中年の危機」は存在するのか
中年の危機は存在しないという考え方を示す研究者もいる。青年期から中年期に至る自我の防衛機制の変化を縦断的に追跡したVaillant(1977)は、35歳以降はそれ以前に比べてストレスの対処方略を発達させ、状況の変化に対する自我の防衛様式がより安定してくることを示した。すなわち、精神の健康とは、人生に問題がないことではなく、問題に対する反応の仕方に規定されるのである(佐藤他、1986)。したがって、たとえ危機的状況に見舞われたとしても、その対処に成功すれば、危機は意識されることはないということになるであろう。同様に、中年の危機は存在しないという主張は、特にパーソナリティの発達研究をおこなってきた研究者によってもなされている。
CostaとMcCrae(1980)は、一連の研究の中で、中年期の苦悩のピークを見つけ出すことはできなかったとして中年の危機を否定した。彼らによれば、中年の危機を体験する人は、他の時期にも同様に危機に見まわれやすい人であって、危機は中年期だけにあるのではないという。さらに、パーソナリティの縦断的研究がいくつか行われているが、その結果の多くも中年期においてはパーソナリティの安定性は高まることを示している(Bengtson et
al.、1985;Kogan、1990)。
パーソナリティの安定度は加齢に伴って高まってくるにもかかわらず、なぜ中年の危機が問題になるのか。中年の危機が特にクローズアップされる背景には、中年期という時期に特有の心理的、社会的な事情を見出すことができるのではないだろうか。
第3章 まとめと今後の展望
第1節 現代社会における成人期
長い間、発達心理学では、成人期は、他の時期に比べて最も安定した時期としてとらえられてきた。しかしながら、最近では成人期の生活は、中年の危機ということばが社会で定着してきたように人生の前半期から後半期に転じる、それは人生の頂点から転じて下り坂に向かうことを意味するが、転換期ともいわれている。
今の成人世代は、世代的に見て板挟み世代と呼ばれている。1つは、家族生活において、戦後の新しい感覚を身につけた子供たちと戦前の時代感覚をそのままもち続けている老親の間にはさまれているのである。板挟み世代としてのもうひとつの意味は、わが国の時代背景の変化からくる社会の変化によっている。現代の成人世代は、明治・大正生まれ世代と戦後生まれの団塊の世代との間にある。 このように現代社会における、成人世代のおかれた立場は、わが国の時代の変遷の影響を他世代よりも強くかつ多く受けており、それらは、成人期の自殺やうつ病の増加、などに反映されているかもしれない。
第2節 今後の展望
中年期というものを、生涯発達的視点で捉え、中年の危機について検討してきた。これまでのところ、「中年の危機」の存在は明確には証明されていないことがわかった。しかしながら、中年期という時期に特有の心理的・社会的な事情があることは、十分に考えられる。今後は、中年期を捉える観点を変えて、動機づけや対人関係、といったもっと様々な点で中年期の研究を進めていく必要があるのではないだろうか。
参考文献
会沢 勲・石川 悦子・小島 明子 編著 1998年 移行期の心理学~こころと社会のライフイベント ブレーン出版
東 洋・繁多 進・田島 信元 編集、企画 1992年 発達心理学ハンドブック 福村出版
ダニエル・J・ロビンソン 著・南 博 訳 1980年 人生の四季
~中年をいかに生きるか 講談社
ゲイル・シーヒィ 著・深沢 道子 訳 1978年 人生の危機~パッセージ プレジデント社
伊藤 隆二・橋口 英俊・春日 喬 編 1994年 成人期の臨床心理学 駿河台出版
村田 孝次 著 1989年 生涯発達心理学の課題 培風館
山内 光哉 編 1990年 発達心理学下~青年・成人・老年期
ナカニシヤ出版
山本 多喜司・S、ワップナー 編著 1991年 人生以降の発達心理学 北大路書房
◇感想をお寄せください。 e-mail:a962332@u-gakugei.ac.jp