「対話型授業研究」の一環として『対話検 meets インプロ』の冊子が完成しました
教師が学習者の立場から授業について考えることは重要です。
それでは、模擬授業に子ども役として参加して「学習者になる」というのは、どういうことだろう。子どもっぽい振る舞いの真似事をすることなのか。そうではないとしたら、それはいったいどういうものなのだろう。そしてそれは、授業を学習者の立場から考えることにどうつながってくるのだろうか。
こうした問いを、教職大学院・総合教育実践プログラムの2024年度のM2院生ら6名が探究し、その軌跡を、同プログラムの渡辺貴裕准教授の監修のもとで冊子にまとめました(A5判、全40ページ)。
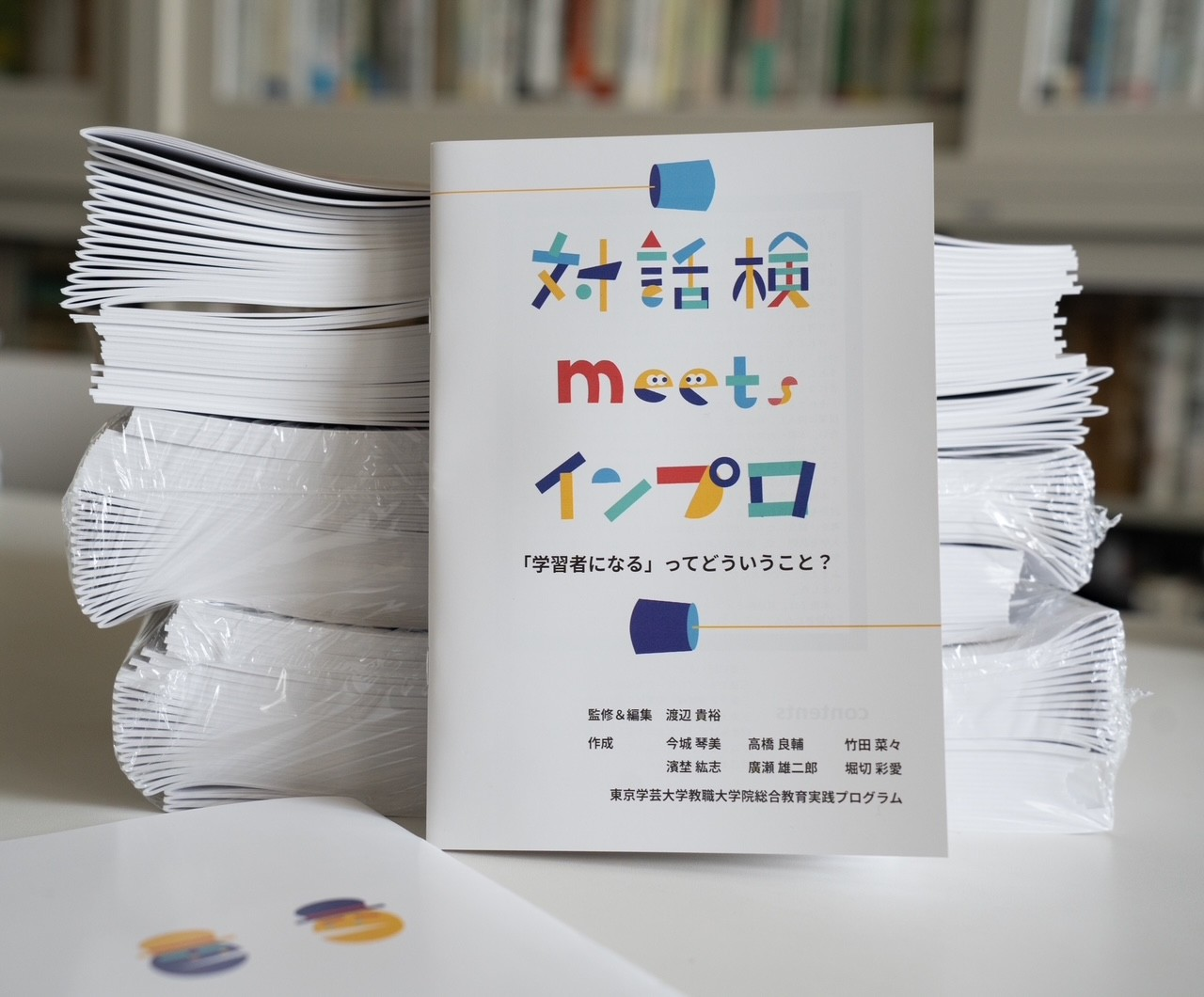
電子版も大学リポジトリの下記リンクからダウンロードできるようになっています。
院生らの探究の出発点となったのは、三重大学の園部友里恵准教授による論考、
「教師が『学習者になる』とはどういうことか インプロの世界からみた『対話型模擬授業検討会』と教師教育」(高尾・園部編『インプロ教育の探究』新曜社、2024年所収)
です。
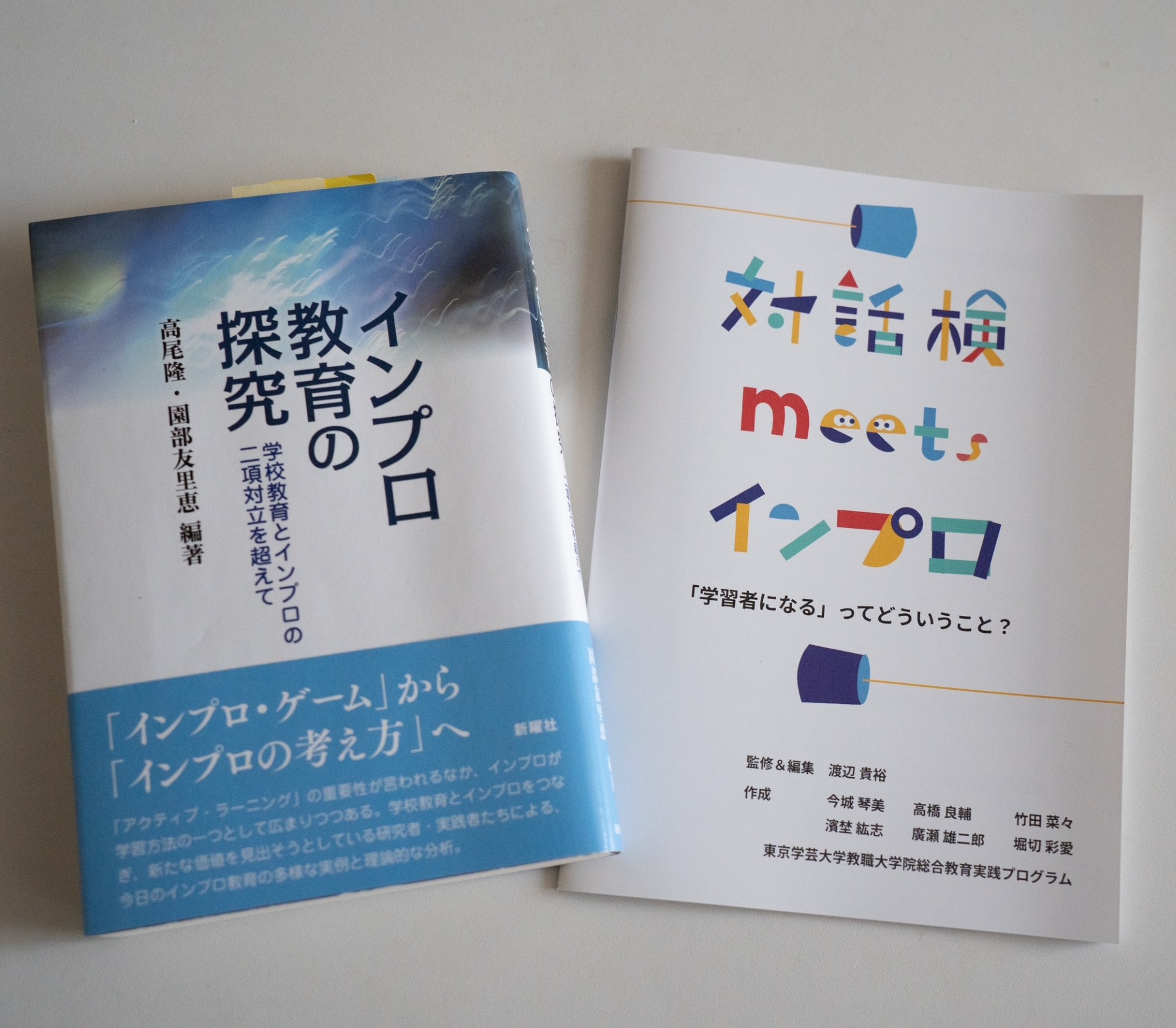
東京学芸大学教職大学院で取り組んできた対話型模擬授業検討会を、園部先生は三重大学において取り組まれ、ご自身の専門であるインプロ(即興演劇)と重ね合わせて、独自の角度から考察を行われました。
それをあらためて、対話型模擬授業検討会のトレーニングをしてきた本学院生らがどう見るか。
院生らが実際に三重大学に行って、園部先生によるインプロワークを経験し、先方の教員や院生のみなさんと一緒に対話型模擬授業検討会を行い、さらにそれをふまえたミニシンポジウムを行って...といった一連のプロジェクトを昨年(2024年)夏に実施しました。今回の冊子はその記録です。
「教育・学習デザイン開発ユニット」の柱の一つ「対話型授業研究」に、他大学とのコラボ、演劇という異分野というように、越境しながらアプローチした成果物です。どうぞご覧ください。
