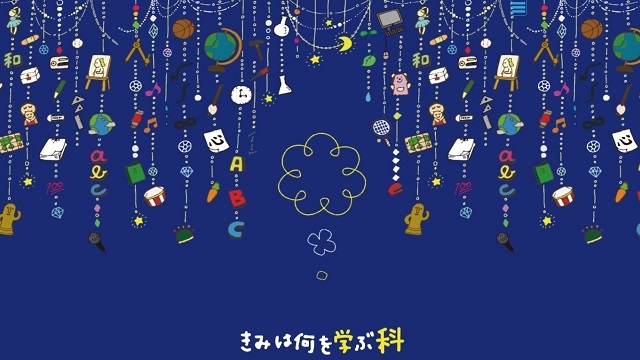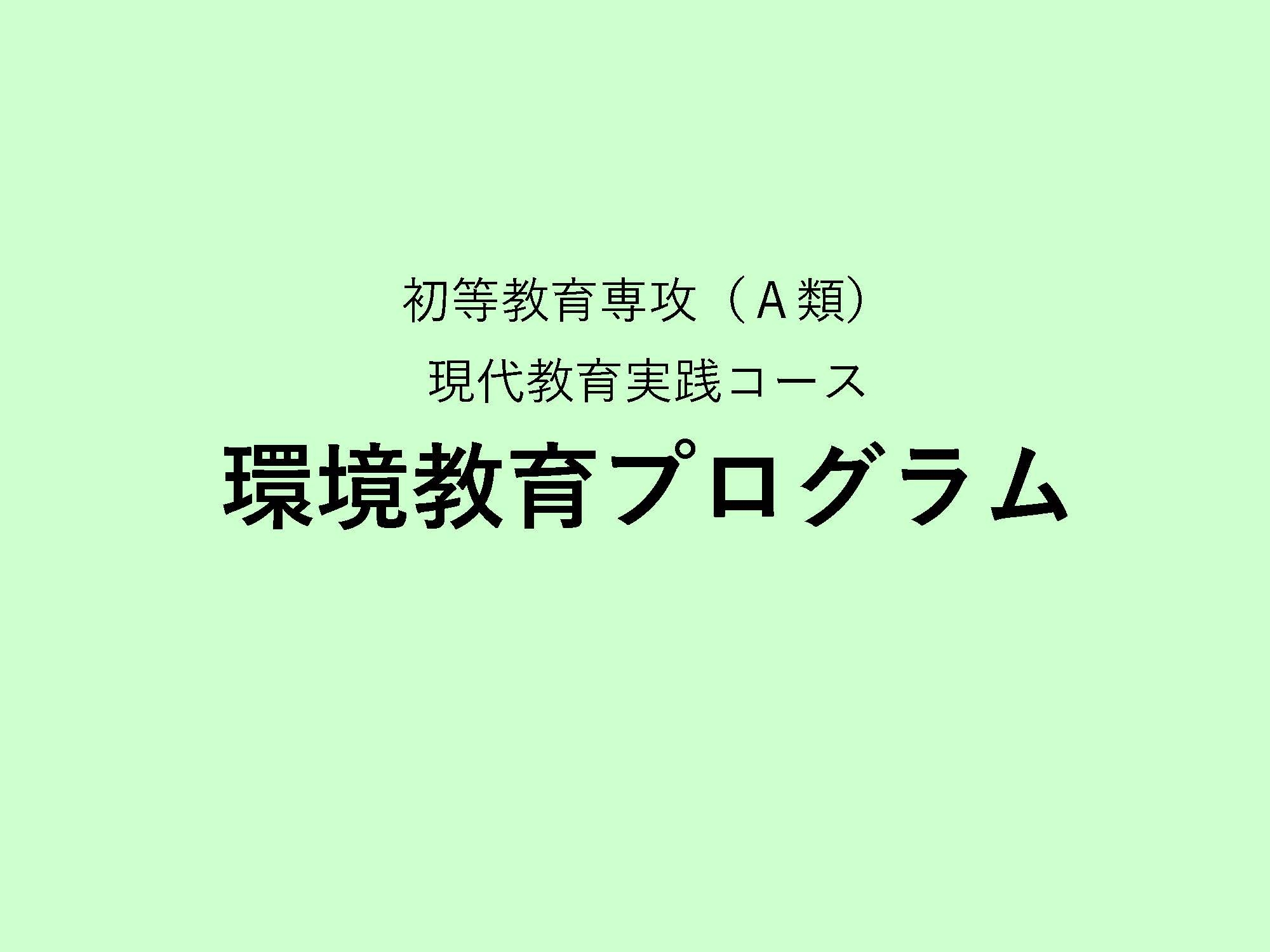学び合いの言葉
フィールドから環境を探る
特色
文系・理系の枠を超えて、領域横断的・総合的に「環境」について学ぶことができます。座学だけでなく、様々なフィールドで実物に触れ、手足を動かし、心と頭を働かせた観賞・観察・測定・調査を通して、体験的に環境リテラシーを身につけ、1人1人の個性に応じた環境マインドを養うことをめざします。
4年間の学び
1、2年次では、教職に関する科目に加えて、「環境」を理解するために自然科学と社会科学の基礎的な知識を学びます。生態系生態学、河川生態学、魚類生理学、植物生態学、保全生態学、景観生態学、環境社会学、自然地理学、環境教育学などの環境に関わる幅広い分野の基礎を学びます。また、野外に出て自然環境を自ら観察・測定・分析し、環境を理解する方法を学び、環境問題を解決するための手段を考えていきます。3、4年次では、それまでの学びを基礎とした実験や実習を通して、さらに環境について理解を深めます。また、3年次には教育実習があります。学び、身につけた知識を教育現場で実践し、「環境を教える」ことについて自分なりの答えを模索する機会になります。そして4年次には、環境教育プログラムにおける学びの集大成として卒業研究に取り組みます。
環境教育プログラムにおける実践の場は教育実習だけではありません。知識や経験を基に、地域の人達に自然環境を伝える技術・方法を考え、実践する機会もあります。また、子どもたちと触れあい、環境を保全する仕組みについて考える場など、実践する機会には困りません。環境教育プログラムは、豊富な教育環境を活用して多くを感じ、考え、そして身につけることで、魅力的・個性的な環境教育観を持った人に成長してもらうことを期待しています。
先輩からのメッセージ
高校生のとき、子供に関わる仕事がしたいと思い学芸大に進学しました。大学では、本当に様々なことに挑戦し、その経験が今につながっていると感じています。所属していた環境教育選修では幅広い専門をもった先生方から、河川での魚類調査や里山での地域交流、人里離れた山奥での実習などの授業を通し「まずやってみる」ことの重要さを教わりました。また、大学院時代は様々な目標を持つ仲間と教育について語り合い、考えるたのしさを知ることができました。こういった時間を持てたことは小学校教員としての原動力になっています。学芸大で学んだことを忘れず、より良い教師になれるようこれからも努力を続けたいと思います。 (吉田安理沙 2020 年度卒業生)
主な進路
小・中・高等学校教員、大学院進学、国家・地方公務員、独立行政法人、企業等
特色ある科目
自然環境調査法、地域の環境観測とその実践、地球環境論、河川環境論、学校教育におけるSDGs、植物進化生態学、環境教育概論、自然体験学習論、環境教育教材論、環境教育カリキュラム論、エコスクール論、環境と教育実践、環境教育野外実習、自然環境解析実験、博物館と展示の活用
学科資料
▼資料



![[A類]初等教育専攻国語コース](http://www.u-gakugei.ac.jp/gbridge/upload/02_002.jpg)