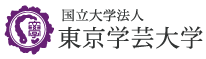「日本盲人社会史研究」(1)
NHKの大河ドラマ「べらぼう」を見ています。NHKのHPによれば、「日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯」ということですが、今ドラマの舞台となっているのは、ほとんど蔦屋重三郎("蔦重")が育った花街吉原です。その吉原の上級花魁"瀬川"、 "蔦重"の密かな恋人である彼女を莫大な金額で身請けする人物として登場するのが、市原隼人さん演じる鳥山検校です。この鳥山検校は、盲人に許されていた貸金業で財を成し、贅の限りを尽くしていたのですが、度が過ぎて、幕府から罰せられることになり、検校の位も財産も剥奪されてしまいます。結局は、瀬川とも別れることになります。江戸時代の日本の盲人男性は、ヒエラルキカルな組織、"当道座"をつくっていました。その頂点にあったのが、検校位で、それは、大名に匹敵するとも言われました。盲人は、先ほど言いましたように、貸金業を営むことができ、それは幕府の庇護も得たもので、阿漕な取り立ても相当にしており、巨万の富を築く人物もいました。そうした盲人の生業が恨みを買うことにもなっていたことは、落語の怪談噺「真景累ヶ淵」などからもうかがい知ることができます。
『日本盲人社会史研究』という本があります。これは、日本近世――江戸時代の盲人の生活を、史料に基づいて丹念に解明した本で、われわれの研究領域における至宝、不朽の名著です。"当道座" のこと――考えてみれば、こうした組織体及び盲人に貸金業が許されていたことは不思議です――は、この本の中心的なテーマとなっています。1974年に未来社から出されたA5型函入上製本605頁の堂々たる大著です(写真)。鳥山検校のことも、この本にちゃんと記されています。度の過ぎた贅沢ゆえに処罰するという申渡書が引かれていて、「べらぼう」の話が史実であることがわかります。この本の著者は加藤康昭先生。先生は、全盲の人でした。
先生は、もともとは理科系へ進むことを希望されていたようですが、旧制一高時代に失明されたために進路を変え、戦後当時、唯一視覚障害者の受験を認めていた東京教育大学(現在の筑波大学の母体)を受験し、入学されました。しかし、入学後も、種々の差別に阻まれて、希望した進路ではなかったのですが、障害をもつ人の歴史研究の道に進まれたのでした。
私は、東北大学の助手でいた1990年に、所属していた小講座の夏の集中講義で加藤先生に来ていただいたことがあります。その頃の東北大学の教育学部は、教授、助教授、助手からなる小講座制という研究組織をとっていて、助手の仕事の一つに、非常勤講師の方の対応がありました。加藤先生は、私が小講座の主任教授である恩師の松野豊先生(故人)にお願いして来て頂いたので、加藤先生に対応することは願ってもないことでした。4日間行われた講義に参加するとともに、先生ご夫妻を宿泊先のホテルから大学まで送り迎えし、大学食堂での昼食をご一緒しました。(この稿続く)

『日本盲人社会史研究』の実物:函から出して立てたところ