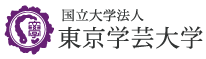令和5年度卒業・修了式式辞
卒業生、修了生のみなさん、ご卒業・ご修了おめでとうございます。昨年、新型コロナウイルスの感染症法上の分類は、ようやく5類になりましたが、いろいろと制限のある学生生活であったと思います。特に、学部卒業生のみなさんは、めぐりあわせとはいえ、入学した時に、新型コロナウイルスのパンデミックとなり、学生生活の半分を、大きな制限の中で過ごさねばならなかったことは、まことに気の毒です。しかし、みなさんは、そうした逆境ともいえる状態の中で、よく学びよく研究し、今日の日を迎えました。その努力に敬意を表したいと思います。また、学長として誇らしくも思います。
さて、パンデミックも収まりつつあるかと思われた今年に入った途端に、能登半島地震が起こりました。人口集中地帯ではなかったためもあって、被害の全貌がすぐには判明しませんでしたが、徐々にその甚大さがわかってきました。発生から2ヶ月が過ぎましたが、いまだライフラインは完全に復旧せず、避難所生活を余儀なくされている方々もまだまだ多くいらっしゃるような状況です。
一方、世界に目を転じるならば、ロシアのウクライナへの侵攻は、いまだ止まず、ガザでは、一般の人たちが、子どもたちも含めて、残酷に追い詰められています。ウイルスや地震のような自然相手ではなく、言葉の通じる人間どうしであるのに諍いを止められないでいます。
こうした必ずしも平穏とは言えない状況の中でみなさんを送り出すのは、まことに残念ではありますが、しかし、考えてみれば、この状況は、これから世に出ていくみなさんが、向き合っていかねばならない世界の課題そのものと言えるのではないかと思います。そこで、ここで、あらためて、整理し、世に出るみなさんに期待することなどを話させてもらいたいと思います。2点ほどあります。
一つ目は、自然と人間の関係のことです。今述べたことで言いますと、ウイルスや地震と人間のことです。新型コロナウイルスのパンデミックが収束に向かう中、そのことにかかわって出された本に『感染症の歴史学』があります。この本の著者は、飯島渉(わたる)さんという方で、青山学院大学の先生ですが、本学のOBです。本学の社会科のご出身で、修士課程まで進んでおられます。この本では、これまで人類を大いに苦しめてきた感染症である天然痘、ペスト、マラリアなどの歴史が取り上げられています。マラリアについての記述の中に、アフガニスタンで献身的な活動をされた中村哲(てつ)医師が、アフガニスタンでもふつうに見られる感染症であるマラリアについて、根絶は不可能なので、感染した時に診てもらえる施設が身近にあることが大切だと考えていたということが紹介されています。人間の命を奪うこともある細菌やウイルスなのだから、天然痘のように根絶・制圧を目指すべきなのではないかとも思うのですが、中村医師はそれは不可能だというところから考えています。飯島さんによると、天然痘は確かに根絶できたのですが、それは例外的で、例えば、天然痘では発疹ができるので、患者の特定が容易だったことや、DNAゲノムを持つウイルスだったので、変異がしにくかったなどの好条件が重なったからだそうです。ウイルスが根絶できないとなると、ウイルスとの共存・共生を考えていくということになります。中村医師が、病気にかかった時に診てもらえる施設が身近にあることが大切だというのは、そういう意味です。新型コロナウイルスと「共生」せざるを得ないポスト・コロナ社会では、「共生」に向けた課題を解決するための努力をしなければならないと、飯島さんは言います。
また、最初に言いましたように、先日、われわれは、大きな地震に見舞われました。地震は、これを根絶することは、まず不可能です。われわれは、「地震に備える」という言い方をしていますが、これは、地震との共存の道を探っていると言ってよいかと思います。今回の能登半島地震は、この備えが充分であったか、改めて検証することを要請しているようにも思います。このウイルスや地震と人間の関係は、自然と人間の調和とも言い換えることができるとも思います。
二つ目は、人間どうしの関係についてです。ロシアがウクライナに攻め入って、3年目となりましたが、戦闘は、いまだ止む気配はありません。ロシアとウクライナは、1991年のソビエト崩壊まで、ともにソビエトに属していた共和国でした。この二つの共和国は、第二次世界大戦ではソビエトとしてナチス・ドイツと闘い、ソビエトは世界で最も多くの戦死者を出しました。その数は、2600万人とも、3000万人とも言われます。この戦死者数には、現在の両国の人たちが含まれています。そうした国と国とが、戦火を交えているというのは、なんとも残念なことです。世界で最大の戦死者まで出して、ナチス・ドイツという巨悪と闘った国の人間どうし、もう一度理解し合えないかと思います。せめて共存ということを認め合えないかと思います。
ソビエトが戦ったナチス・ドイツの行った蛮行の1つが、言うまでもありませんが、ユダヤ人に対するホロコーストです。その死者は600万人とも言われています。そうした蛮行の被害者であったユダヤ人の建国したイスラエルが、テロリストの一掃のためとしても、無辜の人をも、残酷に追い詰めているのにはなんとも失望します。身を置き換えてみることがなんと難しいことかと思い知らされます。
人間どうしの繋がりというのが、なんと脆く、また、人間どうしの理解とはなんと難しいものかと痛切に思います。しかし、であればこそ、粘り強く一層努力を重ねていく必要があると思います。戦争が、戦闘行為が、人を殺し、自分を傷つけ、物を壊し、破壊する不毛な人間の行為であることは言うまでもなく、平和を望まない人はいません。とすれば、人間どうし、共存していく道を探らなければなりません。
ダイバーシティと言われ、生物においても多様性こそ重要といわれていますが、現代を生きるわれわれは、自然とも、人間どうしでも、共存・共生の道が求められていると言うべきでしょう。
本学は、教員養成系大学のフラッグシップ大学と自負しており、実際、文部科学省から指定を受けてもいます。そうした本学で学んだみなさんは、教育に関わる領域ではもちろん、他の領域でも、社会の中でそれにふさわしい貢献をなすことが期待されています。みなさんのそれぞれの持ち場で、われわれ人間・人類が置かれている課題現状を意識し、自然との調和、人間どうしの共存を自らの問題として、プライベート空間も含めて考えていってほしいと思います。安全で平和な中で、みな等しく生きることを謳歌できる社会にしていき、そして、そうした社会を子どもたちに手渡していきたいと思います。
ロシアの革命家トロツキーは、「人生は美しい」と言いました。みなさんも、美しい人生を大いに享受してください。そうであることを心から期待していますが、しかし、いろいろうまくいかないこともあるだろうと思います。行き詰まるときもあるでしょう、また、病気になることもあるだろうと思います。そうした時は、本学と本学の教員を思い出してください。私たちは、いつもみなさんを待っています。みなさんの人生が、みなさんらしく、美しいものであることを祈っています。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。
令和6年3月19日
東京学芸大学学長 國分 充