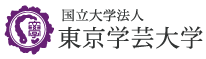令和3年度卒業・修了式式辞(抄)
卒業生、修了生のみなさん、ご卒業・ご修了おめでとうございます。めぐりあわせとはいえ、コロナ禍の2年間、それが明けないうちに卒業、修了の年を迎えたこと、なんとも気の毒です。特に、大学院のみなさんには心残りもある2年間であったと思います。しかし、そうした逆境ともいえる状態の中で、あなた方は、よく学び、今日の日を迎えました。その努力に敬意を表します。
(略)
さて、フランスの哲学者・作家であるカミュの小説に「ペスト」という作品があります。これは、彼の代表作ともされる作品で、1947年に書かれました。ペストが蔓延し、閉鎖されてしまった都市、アルジェリアのオランの人々の姿を描いたものです。この作品は、コロナ禍になってよく読まれるようになったと聞いています。描かれている状況が、現在のわれわれが置かれている状況とよく似ているためだと思います。私も、この本について、また、作者であるカミュについて、昨年の卒業式、入学式で触れてきました。
この小説は、感染症という天災の不条理の他、信仰や倫理、友情、愛情のことなどを含む非常に重厚な作品です。が、その中心となっているのは、感染が始まり、拡大する中、病気に対するに十分な手立てもない中でペストに立ち向かう青年医師リウと、彼に協力して、ともに闘う仲間のタルーの姿です。
この小説にはいろいろと心に残ることがありますが、リウが、ペストとの勝負において、人間は知識と記憶をかちえたと言うところなどもそのひとつです。リウは、結局は、ペストと一緒に闘ったタルーをそのペストで失い、ペストとは、自分にとって際限なく続く敗北だと言いながらも、自分はペストを知った、そして、それを忘れない、また、友情を知った、そして、それを忘れない、さらに、愛情を知った、そしてそれをいつまでも忘れないにちがいないと言い、ペストと生命との勝負で、人間は、知識と記憶を勝ちえたと言います。
この言葉の意味を考えてみれば、リウが言う知識と記憶の形式を整え、公共に資するものにしたひとつの形が科学です。みなさんも、大学、大学院で、その作法を学んだと思います。これによって、人間は、不条理と思える事柄から解放されるべく努めてきました。このコロナ禍でいえば、例えば、感染防止の様々な対策です。
また、この知識と記憶というのは、人の慈しみ方、愛し方の作法でもあります。リウが、ペストのことを言った後に、友情のことを言い、そして、愛情のことを言っているのは、このことだと思います。人は、知り合って、心にかける、時に思い出す、これが人を慈しむということであり、人を愛するということだと思います。思えば、人はこうして人に元気づけられ、元気づけ合い、世界に立ち向かい、不条理と闘ってきた、闘っているのだと思います。人は、誰かとともに、誰かと同伴して闘っていくことができるということをあらためて心に刻みたいと思います。
知識と記憶によって、人間は、直にこの新型コロナウィルスを克服するでしょう。ワクチンもでき、特効薬もできてきています。現在、社会は、目に見えないウイルスにより疲弊し、鬱屈した状況となっています。しかし、明けない夜はありません、いずれ夜は明けます。今少し辛抱しましょう。
今後あなた方は、社会に出て、学生時代に増して、若さを享受し、活躍していくことになると思います。ロシアの革命家トロツキーは、人生は美しいと言いました。美しい人生を大いに享受してください。そうであることを心から期待していますが、しかし、いろいろうまくいかないこともあるだろうと思います、行き詰まるときもあるでしょう、また、病気になることもあるだろうと思います。......(略)......そうした時は、本学を思い出してください。あなた方を慈しんだ本学と本学の教員は、あなた方を忘れません。いつでもあなた方を待っています。あなた方の人生が、あなた方らしく、美しいものであることを祈っています。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。
令和4年3月18日
東京学芸大学長 國分 充