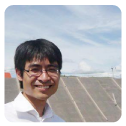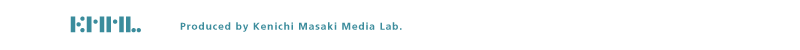フランス美女と寿司列車の旅
モンゴルで生活していた頃、首都にある寿司屋を何度か訪れたことがある。それは確か、大学通りと呼ばれる道の脇にある店で真っ黒の建物だったと思う。大学通りはモンゴル国立大学という立派な大学を貫くように敷かれた道で、スフバートル広場の真横を南北に走っている。ただし、これは記憶が間違っていなければの話だ。しかもモンゴルの街はビルが建ったりして頻繁に風景が変わるので、もうすでに大学通りなどないのかもしれない。少なくとも半年前にはあったはずだが。
あるとき、その寿司屋で同席していたオーストラリア人女性に尋ねられた。「寿司列車を知っていますか」。日本で30年以上生きてきて初めて聞く言葉だった。豪華なシベリア鉄道か何かの食堂車の中で寿司が豪勢に振る舞われるといった物珍しい話なのかなと思ったが、そうではないようだった。彼女の言った言葉は ‘Sushi Train’ なので、私はそれを直訳して「寿司列車」と書いたのだが、この翻訳が間違っていることはあとで説明を聞いて分かった。オーストラリア英語で ‘Sushi Train’ は回転寿司を意味するのだ。なるほど……と何人かの人は膝を打ったかもしれないが、これは辞書にも出ているような広く知られた言葉だそうで、既にそれを知っている人は、この文章を書いている奴はなんて無知なんだろうと思われただろう。言語とは不思議なもので分かってしまえば何でもないことが、分からないと物凄くおかしな想像をしてしまうものなのである。
大学通りにあるその寿司屋にはあいにく寿司列車の線路はなく、店の人が皿をいちいち運んでくるスタイルのものだったために、‘Sushi Train’の話題はあまり深まることがなかったが、もしかしたら経済発展の著しいウランバートル市のことだから既に ‘Sushi Train’ が市中を走り回っているのかもしれない。ちなみにオーストラリアを私は訪れたことはないが、彼女によれば、その国では寿司列車は非常に人気なのだそうだ。
ところでここはイギリスなので、イギリスの話に移る。
先日、知り合いのイギリス人学生たちと食事に出かけた。日本人である私が来るというので、寿司屋に行こう、という話になった。駅の近くにある繁華街には寿司を出す店が何軒かあって、その一つを訪れた。そこには寿司列車が静かに走っていた。我々の一行に、とてもきれいな女子学生がいて、彼女はこれまでに二度、日本を訪れたことがあると言った。彼女は、お好み焼きが好きなのと嬉しそうに語り、いただきます、という言葉やいくつかの知っている単語を、覚えたての初々しい雰囲気を醸し出しながら私に言って聞かせた。彼女はフランスに生まれたが、英国に育ち、両方の国の言葉を話すことができるのだと自身を説明した。今は英文学を学んでいるのよと言い、隣にいた別のイギリス人が、こいつはハリー・ポッターの研究をしてるんだぜ、と冗談を言うと、違うわよ、シェークスピアよ、と慌てて訂正した。そうした退屈なやりとりも彼女の美貌が、とても華やいだものしているのだった。
彼女の透き通るような薄い茶色の瞳を眺めていると、いろいろと聞き逃す単語が多くなり、それはそれで大変に困る事態であった。それに加えて、早口に続く彼女の完璧な英語についていくことは簡単ではなく、理解しかねる部分も多くあったが、ときおり説明をしてくれる隣の男子学生のお陰で話から取り残されずに済んだ。彼女に「納豆」を試したことはあるかと尋ねると、私、ナットウは食べられないわ、と悲しそうな表情で答えた。彼女の洋服の美しい花柄がその表情をより哀愁のあるものへと演出しているようで印象的だった。
日本の回転寿司屋と同様、おもむろに寿司が皿に乗ってこちらに向かってくる。そして通り過ぎる。列をなした寿司が、貨物列車のように見えてくる。厨房へと繫がるトンネルの中にそれらは、消えていく。おびただしい数の皿が通り過ぎていった。それほどバラエティに富んでいるとは言えなかったが、それでも多くの種類の皿が私たちの目の前を横切っていく。
そのときだった。突然、満面の笑みで彼女はひとつの皿を取り上げた。それは、どら焼きであった。どら焼きといっても中にはカスタードクリームが入っていて小豆は入っていない。それにクランベリーソースがどっさりと乗せてあるのだった。説明書には確かにどら焼きと書いてあるので、これはどら焼きであることに間違いはないが、それは極めてイギリス的な食べ物なのかもしれなかった。彼女は、みそ汁と、どら焼きの皿を左右に並べて嬉しそうに食事に取りかかろうとした。それは、常識を越えた光景のように見えた。しかも日本人の私には、どういう訳かその姿が不憫にさえ見え、意を決した私は「言いにくいのだけど、組み合わせとして、かなりヘンだよ、それは。」と教えてあげた。彼女はそんな親切な忠告に対し、笑顔をこちらに見せただけでそのまま『食事』を続行してしまった。「私、いつもヘンなの」とだけ彼女は答えた。
一応、それを最後まで見届けなければならない、という無用な責任感に、私は、苛まれることになった。
そもそも、この文章は、フランス人美女と突然、素敵な恋に落ちるという類いのストーリーではない。大変、申し訳ないのだけれど、そういう都合のいい話は滅多に起きないのだ。一生に一度あれば、とても幸運というべき程度のもので、私ごときの人間には、こういうおかしな結末しか待っていないのが常だ。彼女がさも満足げに、みそ汁を飲み終えたあと、しばらく雑談をして、私たちは寿司屋を後にした。寿司列車は、相変わらず静かにゆっくりと走っていた。
▼Vol.009の原稿が届きました!寿司列車も気になりますが、フランス美女も気になります^ ^