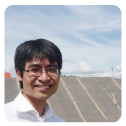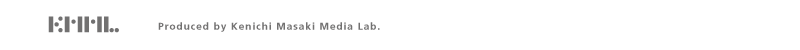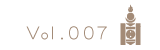
街の様子。地面が凍っていて滑りやすい。向こう側にはヨーロッパ調の建物がつづいている。
外はマイナス30度。モンゴルのイベントへ。
ウランバートル市はいよいよ最も寒い時期となった。まるで冬山に挑戦するような服装で外に出かける。上着にはダウンの入った分厚いコート。ズボンの下には厚手のタイツを履く。靴は、底が厚く内側に毛がついている暖かいものを。できれば、くるぶしが隠れるブーツがいい。耳まで覆うことのできる帽子をかぶる。手袋はカシミア製のものがいいと思う。これくらいの装備があれば、屋外を歩いても、ひとまず大丈夫だ。それでも、無防備の顔には冷えきった空気が容赦なく突き刺さる。睫毛が凍り、頬に痛みを感じる。鼻で空気を吸い込むと、なぜか少し息苦しい。まるで空気までもが凍っているみたいだ。マフラーをまいて、口元を隠すようにして歩けば少し暖かい。けれど、吐いた息に含まれる水蒸気が瞬時に冷えるので、マフラーもすぐに凍り付いてしまう。それが摂氏-30度の世界だ。
そういえば、このごろ美しい青空を見かけることがあまりない。寒さに支配された真冬のウランバートルは街中から彩りが失われて少し寂しげだ。ずいぶん前に葉の落ちてしまった並木もグレー色になって立ち尽くしている。地面を見るとスケートリンクのように氷が道路に貼り付いてる。モンゴル人でさえ、しばしば転んでしまうほどだ。投げ捨てられたコカ・コーラのボトルの中に目をやると、残ったコーラが固く凍っているのが見える。その傍で、小さな黒い野良犬が忙しく何かを探している。彼らはどのようにして夜を過ごしているのだろうとふと考えてしまう。
でも、冬のモンゴルが身も心もすっかり灰色の世界に成り果ててしまう訳ではない。モンゴル人はこんな寒い季節にこそ、心を踊らせるためにお祝いごとをして楽しむようだ。例えば「シンジリーン・バヤル」というお祝いが年末にある。「シンジリーン・バヤル」は直訳すると「新年のお祝い」という意味だが、とにかく年末に開催される。新年を迎えるためのイベントなのだろうか。職場の仲間や友人たちがそれぞれに企画し、レストランなどに会場を予約して一大イベントを繰り広げることになっている。
12月23日は僕が通う学校が主催した「先生たちのシンジリーン・バヤル」だった。教師が一同に集った。同僚の女性たちは艶やかなドレスを美しく着こなす。中には、もとの姿が判明しないくらいの人もいたほどだ。男性も皆、盛装だ。テーブルにはコース料理が供された。それぞれの出し物を見物し、ワインやビール、シャンパンとともに楽しむ。時期が重なるためか、クリスマス・ソングもひっきりなしに流れている。大多数のモンゴル人にとってクリスマスは宗教的な意味合いがないようだが、クリスマスのスタンダードナンバーを歌うなど、積極的にそれを楽しんでいるのが分かる。サンタクロースの格好でプレゼントを配り歩いている教師もいた。モンゴル人は社交ダンスを好み、この日も皆が陽気に踊っていた。僕にはそうした嗜みがなく、交わることはできなかったが、それでも十分楽しむことができた。そのようにして華やかな時間が過ぎた。
シンジリーン・バヤルの様子。大きなレストランの中央に集まり、これからダンスが始まるところだ。
あるとき、司会者がこれからゲームをすると言い出した。いまから指名する男性諸君はステージに上がって下さい、と言っている。何人かの男性が選ばれ、壇上に上った。もう一人くらいいたほうがいいですね、と司会者が辺りを見回した。僕は目が合わないように気をつけていたのだが、彼は案の定、僕を指差し、あなた、どうぞと言った。外国人の僕には彼らの言っていることの大部分が分からないし、モンゴルのゲームのルールも知らない。正直のところこの指名は遠慮したかった。しかし、酒気を帯びた観衆がそんな気遣いをするはずがなく、僕は拍手喝采の中、ステージに上がらされた。司会者が早口にルールの説明をしているが、全く理解できなかった。額に汗が滲んだ。ときどき沸き起こる大爆笑がいっそう僕を追いつめた。これからどのような辱めに遭わされるのか。
では、「スタート」と司会者が言った。僕が呆然と立ち尽くしていると、隣の太った男性がジャケットを脱いだ。そしてそのまま、革靴を脱ぎ捨て、次にネクタイを外した。これからとても恐ろしいことが起こるような気がした。気づくと、司会者が僕を見て何やら叫んでいる。「さあ、日本人のあなたも早く早く」。僕は苦笑いをして、ごめんなさい、ステージを降りてもいいだろうかとジェスチャーで合図した。そこにいることが苦痛だった。横を見ると、隣の太った男性は上半身がすっかり裸になるまで服を脱ぎ、次にズボンに取りかかろうとしているところだった。僕はひとまず、ジャケットを脱いでネクタイを外した。いいぞいいぞ、と観衆が叫んでいる。ハンカチで汗を拭い、哀れな表情をしていると、ようやく一人の女性教員が、あなた、もういいわよ、席に座って。とステージの下から僕を救ってくれた。おいおい、しょうがねえな、と酔っぱらった男性教員が僕に野次を飛ばしているのが聞こえる。始末に負えない状況だった。僕はどうやらこのゲームの面白さを台無しにしてしまったようだ。結局のところ、そのゲームは最終的に社交ダンスの形式に変化していき、皆、楽しむことができたようだった。だが、このゲームの主旨やルールについては、今でさえ僕にはよく分からないままだ。
アメリカから英語を教えに来ている教師が「さっきは大変だったわね」と声をかけてくれた。同じ外国人としての気持ちを察してくれたのだった。彼女もまた、モンゴルの習慣や言葉がまだ十分に理解できないのだと言っていた。
華やかなときにこそ、一緒に楽しみたいものだけれど、そこに文化や言葉の大きな壁が立ちはだかってしまうことがある。マイノリティ(少数派)とマジョリティ(多数派)の間に深く根を下ろしている問題というのは、こういう些細な場所にふと顔を覗かせるものなのだろうか。と、こんな場所で、ずいぶん深刻なことを取り留めもなくつらつら考えているうちに、パーティは幕を閉じた。この日、僕はモンゴル人に強制されて、何度かウォッカの一気飲みをした。これもモンゴルで好まれる悪ふざけのひとつだ。僕はできる限りのことをしたつもりだし、それで皆も喜んでいた。この国では彼らのやり方を尊重しなくてはならないと思う。けれど、できないことがある。それは、まあ、仕方ないかなと思っている。自分の能力を越えたことはできないのだから。
ウォッカのせいで朦朧となった意識は、酔った同僚の友人と一緒にタクシーを拾って行き先を告げる頃には少しましになっていた。外気が冷たいと思った。
街の中心地、スフバートル広場に飾られた大きなクリスマスツリー。
12月25日が過ぎてもモンゴルではクリスマス雰囲気が続いている。
▼Facebookと連動した掲示板を設置しました。桐山さんへのメッセージよろしくお願いします。