教員の書籍・教材
東京学芸大学ではいろいろな機関と連携して、さまざまな研究を行ってます。また東京学芸大学の各教員の研究も膨大な数になります。ここではそれらの中から、新しい研究、先進的な研究を紹介します。 現在は東京学芸大学の教員の書籍のみ紹介しています。
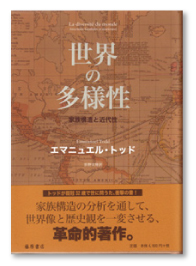
タイトル
『世界の多様性』
著者
エマニュエルトッド(著)
荻野文隆(訳)
出版社
藤原書店
ISBN
978-4894346482
発行日
2008年9月22日
定価(税込)
4830円
内容
世界の多様な家族構造の分析を通して世界像と歴史観を一変させた世界的な人類学者エマニュエル トッドの主著。 家族構造とイデオロギーの関係、女性の地位と教育力との関係、そして経済成長との関係を地球規模の視野のなかで分析した画期的な本です。 様々なレベルでの格差の拡大が世界を翻弄している今日、人々の基本的なつながりと生活をもとにした社会のあり方、教育のあり方を考えようとするとき、多くのヒントを提供してくれる本です。
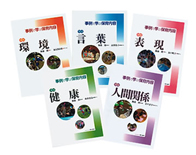
タイトル
「事例で学ぶ保育内容シリーズ」
著者
無籐隆(監修)
<領域> 健 康 :倉持清美(代表)・河邉貴子・田代幸代(編者)
<領域> 人間関係 :岩立京子(代表)・赤石元子・高濱裕子(編者)
<領域> 環 境 :福元真由美(代表)・浜口順子・井口眞美(編者)
<領域> 言 葉 : 高濱裕子(代表)・倉持清美・伊集院理子(編者)
<領域> 表 現 :浜口順子(代表)・松井とし・岩立京子(編者)
出版社
萌文書林
ISBN
健康:4-89347-096-5
人間関係:4-89347-097-3
環境:4-89347-098-1
言葉:4-89347-099-x
表現:4-89347-100-7
発行日
2008年9月15日
定価(税込)
2100円
内容
東京学芸大学・お茶の水女子大学の大学と附属幼稚園の協同による保育者養成テキスト発刊
2006年12月20日に、東京学芸大学・お茶の水女子大学の大学教員と附属幼稚園教員の協同編集・執筆による新しい保育者養成テキス ト「事例で学ぶ保育内容シリーズ」(無籐 隆監修、全5巻)が萌文書林より発刊されました。
本シリーズには、次の5つのきわだった特徴があります。
1.幼稚園の実践のあり方がわかるように、子どもの遊びや指導のあり方が浮かび上がる写真をフルカラーで活用しています。
2.東京学芸大学附属幼稚園とお茶の水女子大学附属幼稚園における長年の実践知が、写真と解説により明らかにされています。
3.学芸大・お茶女大の大学・附属園の連携による「幼児教育未来研究会」での現職研修の実績をもとに、研究者と実践者との対話を 通じて編集されました。
4.実践と理論の往復・対応に意識して執筆されています。
5.新しい幼稚園教育要領の改訂の方向を反映させています。
(無籐隆「シリーズまえがき」参照)
本シリーズは、将来の保育者を志す大学・短大・専門学校の学生のテキストとしてだけではなく、現職者の豊かな保育実践の創造に も資するものとして、また、教育実践研究を行う大学院生にも参考になるものとして発刊されました。
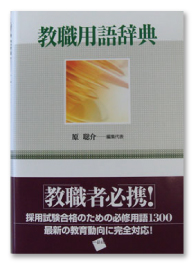
タイトル
『教職用語辞典』
著者
原聡介(東京学芸大学名誉教授)(編集代表)
陣内靖彦(東京学芸大学教授)、高橋勝(横浜国立大学教授)、橋本美保(東京学芸大学准教授)、浜田博文(筑波大学准教授)、水内 宏(聖母大学教授・千葉大学名誉教授)、矢田貝公昭(目白大学教授)(編集委員)
出版社
一藝社
ISBN
978-4901253147
発行日
2008年4月22日
定価(税込)
2625円
内容
この辞典は本学および連合大学院の構成大学関係者を中心とした執筆者で作られています。
編集委員はこれまで教員養成に深くかかわってきた経験を持っています。また、執筆者もそれぞれの領域で優れた専門的知見を供えている人たちであり、そのほとんどは本学教員、旧教員、卒業生、連合大学院関係教員です。
本書は教職の現職者(教育行政職関係者を含む)、新しく教職を志す採用試験受験者、教育学部・教職課程で学ぶ学生のための学習・実践・研究の手引きとなるよう編集されています。特に、教員採用試験合格のための必修用語1300を取り上げて解説、教育基本法改正以後の最新の教育動向に完全対応しています。

タイトル
『多言語多文化社会へのまなざし―新しい共生への視点と教育―』
著者
赤司英一郎・荻野文隆・松岡榮志(編)
出版社
白帝社
ISBN
978-4-89174-917-0
発行日
2008年3月31日
定価(税込)
2730円
内容
本学の18名の教員(内1名は現在、東京大学大学院准教授)によって執筆された、多元的な国際社会・文化へのユニークな入門書です。
人々の生き方や社会の多様な姿に、文化、思想、歴史、芸術など様々な面からのアプローチを試み、地球規模での価値感や歴史の多様性を多角的な側面から分析する。日本社会の内なる多様性と他者との共生への歩み方を探る。
「はじめに」より
「このように多様な社会と文化の状況、このような異文化間の交流、そして、このような他者と異文化にまつわる歴史によって国際社会が形成されてきたこと、現在も形成されていること、さらに、その中に暮らす私たちが学校の中でも、このような他者と異文化にまつわる問題に直面しながら、新しい共生への視点を探し求めていることを、多くの学生に、そして外国文化のなかで育った児童・生徒と日々接しておられる小学校・中学校の先生方に、共に考えていただけたらとおもいます。」

タイトル
『カナダのメディア・リテラシー教育』
著者
上杉嘉見[教員養成カリキュラム開発研究センター](著)
出版社
明石書店
ISBN
978-4-7503-2717-4
発行日
2008年2月 8日
定価(税込)
6510円
内容
私たちは,テレビや雑誌,広告といった様々なマスメディアに囲まれて生活しています。また,ショッピングモールやコーヒーショップも,現代社会にとって大きな意味を持つメディアです。こうした,生活環境そのものとなったメディアが,どのような立場から何を訴え,人々の価値観にいかなる影響を与えているのかを考え,自分自身とメディアの関係を冷静に見直すことを目指すのが,メディア・リテラシー教育です。これは,最終的には一人ひとりの世界に対する認識と関わり方を変えることにつながるかもしれません。
本書は,最も先進的と言われるカナダのメディア・リテラシー教育が,日本の学校教育に対して持つ意味を,イギリス発祥のメディア・リテラシー論の系譜も視野に収めつつ,明らかにしようとするものです。マスメディアの商業主義批判を軸に展開されるカナダのメディア・リテラシー教育が,読者に知的刺激と希望を与えるものとなるよう,切に願っています。


