教員の書籍・教材
東京学芸大学ではいろいろな機関と連携して、さまざまな研究を行ってます。また東京学芸大学の各教員の研究も膨大な数になります。ここではそれらの中から、新しい研究、先進的な研究を紹介します。 現在は東京学芸大学の教員の書籍のみ紹介しています。

タイトル
『江戸の教育力― 近代日本の知的基準』
著者
東京学芸大学 教授 大石学(著)
出版社
東京学芸大学出版会
ISBN
978-4-901665-08-7
発行日
2007年3月30日
定価(税込)
1260円
内容
NHK大河ドラマ「新選組!」の時代考証もした江戸時代史の達人、東京学芸大学の大石学教授が書いた江戸時代の教育に関する本。幕府の教育政策から子供たちの寺子屋での様子までいきいきと、わかりやすく描かれているため、庶民の教育熱が高く7万もの寺子屋があったと言われる江戸時代の教育状況がよく理解できます。
「意外や意外、江戸時代は武士も農民も町人も
上下の別なく教育熱が高かった―。
武士の子弟が通う藩校は全国で300近く、
庶民の手習所(寺子屋)はなんと約7万とも。
当時の外国人も驚いたその教育の広まりは、
実は明治以降の急速な近代化を支えたものでもあった。
江戸時代を「初期近代」ととらえる、新たな見方を示す一冊。」(本書より)
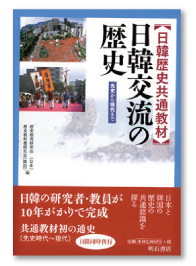
タイトル
『日韓交流の歴史』
著者
歴史教育研究会[日本](編)
歴史教科書研究会[韓国](編)
出版社
明石書店
ISBN
978-4750324838
発行日
2007年2月22日
定価(税込)
2940円
内容
●歴史教育研究会(日本)、歴史教科書研究会(韓国)編
東京学芸大学と協定校ソウル市立大学との10年間に及ぶ学術交流の成果。 両校の教員と卒業生合計40名による徹底討論でできあがった共通の叙述。 日韓の交流の歴史を先史時代から現代まで通史として描いた日本最初の試み。 民間の立場から、日本と韓国の歴史の共通認識を探る。
「真実を粗末にする歴史は、歪められた歴史であって、相手国に対する文化の侵略ともいえます。そこから生まれた誤った歴史認識は、偏った人間を作り出し、それでは自分の正しい自画像も描けなくなるでしょう。それはとても悲しく不幸なことです。」(本書、「刊行にあたって」より)
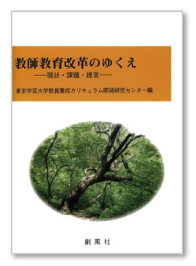
タイトル
教師教育改革のゆくえ-現状・課題・提言-
著者
東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター(編)
出版社
(株)創風社
ISBN
978-4883521203
発行日
2006年12月 1日
定価(税込)
1890円
内容
本書は、本学教員養成カリキュラム開発研究センターがこれまで行ってきた様々な共同研究の成果に基づく書籍である。学校教育、教員養成、教員研修のそれぞれの現場でいま何が起こっているのかを明らかにしながら、それぞれの現場が抱える課題を描きだしていく。そして、これからの教員養成の政策、システム、カリキュラムへの提言を行う。

タイトル
『小林弘珪藻図鑑 第1巻 -Dr. H. Kobayasi's Atlas of Japanese Diatoms Based on Electron Microscopy. Vol.1』
著者
東京学芸大学准教授 真山 茂樹 (共著)
出版社
内田老鶴圃
ISBN
9784753640461
発行日
2006年11月14日
定価(税込)
35700円
内容
珪藻分類の第一人者であった故小林弘東京学芸大学教授の名を冠した、電子顕微鏡写真を中心に据えた本格的な図鑑。和文と英文からなる。
珪藻は池、川、海といったあらゆる水域に暮らす単細胞性の生物である。その細胞はガラス質の殻で覆われているが、その形やそこに刻み込まれた模様は実に多様であり、ミクロの芸術を彷彿させるるものがある。
かつて我が国には珪藻の図鑑が存在せず、人々はその分類に手を焼いていた。今から30数年前、小林弘博士は珪藻の図鑑を作るべくプロジェクトを開始したのであった。しかし、我が国は珪藻研究では後発国であり、重要な標本はすべて海外にあったため、その作業は難航した。そして1996年、小林博士は図鑑の完成を見ることなく70年の生涯を閉じたのである。その後、博士に師事した本学の真山茂樹准教授を中心とする4人の研究者がこれを引き継ぎ、ようやく完成したのがこの図鑑である。4人の研究者は皆、学芸大学出身であり、使用した電子顕微鏡も本学保有の物。まさに学芸大学パワーで作られた図鑑である。
本図鑑では、電子顕微鏡観察による詳細な微細構造の観察に基づいて珪藻の分類が行われた世界でも類を見ないものである。また、本書では全種類の水質汚濁耐性が記されているほか、約半世紀にわたり著者らが記録した出現地が記載されており、分類学だけでなく生態学的にも貴重な資料を提供している。
珪藻殻の造形は見ていて飽きない美しいものである。専門の研究者でなくとも、一度本書を手にとって、ミクロの神秘を肌で感じ取りたいものである。

タイトル
『音楽の文章セミナー』
著者
久保田慶一(著)
出版社
音楽之友社
ISBN
978-4276101500
発行日
2006年9月15日
定価(税込)
1995円
内容
音楽を文書で表現するために
音楽ブログ、曲目解説、ライナー・ノート、演奏批評、作品分析、学位論文・・・
音楽について書くときに必要な心がまえ、知識、情報源などをわかやすく解説!


