教員の書籍・教材
東京学芸大学ではいろいろな機関と連携して、さまざまな研究を行ってます。また東京学芸大学の各教員の研究も膨大な数になります。ここではそれらの中から、新しい研究、先進的な研究を紹介します。 現在は東京学芸大学の教員の書籍のみ紹介しています。
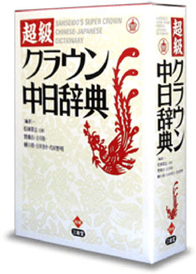
タイトル
『超級クラウン中日辞典』
著者
松岡榮志[アジア言語・文化研究分野教授](主幹)
錦昌・古川裕・樋口靖・白井啓介・代田智明 (著)
出版社
三省堂
ISBN
978-4-385-12188-8
発行日
2008年2月 1日
定価(税込)
6300円
内容
総項目数91,500(親字11,500、熟語80,000)
- ●親字には中国の通用字7,000字を完全収録。すべての親字に部首・画数・四角号碼などを表示
- ●現代の息吹をあざやかに伝える有力新聞3年分の全記事からなる中国語コーパスを活用
- ●中国政府認定の新語や政治・経済・医学・ITなどの術語が充実
- ●親字・見出し語に品詞を明示。(~儿)や(~的)で派生語を表示
- ●由来 参考 表現 用法 などの豊富な参考情報。「同義語」「反義語」も充実
- ●初学者にも使いやすい「音訓索引」「部首索引」「総画索引」
【超級クラウン中日辞典の内容】
[重要親字]使用頻度の高い重要親字は囲み記事で用法・豆知識などわかりやすく解説。
[日中小辞典]内容充実、意味の違いや句例も表示。
[多彩な付録]文化情報(映画、流行歌、京劇など)・発音解説・各種地図(行政区画、方言、歴史など)会話表現集・祝祭日一覧・レファレンス案内ほか。
[挿絵]人物・しぐさ・楽器・生活用具など中国の雰囲気を伝える挿絵を満載。
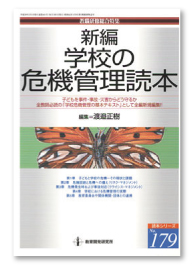
タイトル
『新編 学校の危機管理読本』
著者
養護教育講座 渡邉正樹(編著)
竹鼻ゆかり,鈴木琴子他(著)
出版社
教育開発研究所
ISBN
978-4-87380-975-5
発行日
2008年1月 1日
定価(税込)
2310円
内容
本書は,教職員が現在かかえている,あるいは今後出あう可能性がある様々な危機管理の課題も取り上げ,それらへの具体的な対策を提案する。
<第1章>「子どもと学校の危機,その現状と課題」では,子どもたちや学校を巻き込む事件・事故の実態とその原因を明らかにする。犯罪被害はもちろん,学校の管理下の災害,交通事故,自然災害,性行動など様々な問題を取り上げている。
<第2章>「危険回避と危機への備え」では,危機管理の最初の段階として,危険を早期に発見すること,危険をいち早く取り除くこと,そして危機発生を未然に防ぐという視点から,教職員らが身につけるべき危機管理の内容を示す。ここでは情報モラル教育,性教育,自殺防止などについても取り上げている。
<第3章>「危機発生時および事後対応」では,実際に危機発生時および危機発生後を想定して,教職員,保護者・地域住民,関係諸機関が取るべき対応を示す。事後の対応として重要な心のケアやマスコミへの対応についても取り上げている。
<第4章>「学校における危機管理の実際」では,学校に必要とされる危機管理体制や教職員が身につけるべき能力に焦点を当て,推進すべき危機管理の実際について紹介している。教職員への危機管理研修の内容・方法についても取り上げている。
<第5章>「教育委員会や関係機関・団体との連携」では,学校・教職員を支援する教育委員会や学外の関係機関の役割について紹介している。ここではICTの応用など危機管理に関わる最新の動向も取り上げている。
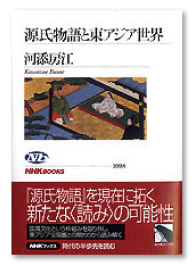
タイトル
『源氏物語と東アジア世界』
著者
東京学芸大学教授 河添 房江(著)
出版社
日本放送出版協会
ISBN
9784140910986
発行日
2007年11月29日
定価(税込)
1218円
内容
『源氏物語』を現在に拓く新たな<読み>の可能性。 国風文化という枠組みを取り外し、東アジア交易圏との関わりから読み解く。 光源氏は、なぜ「光る君」なのか? 「あなかしこ、このわたりに若紫やさぶらふ」と『紫式部日記』に記されて千年。 以来、日本固有の美意識の源流として称揚されてきた『源氏物語』だが、果たして、本 当に和の文学の極地と言えるのか。 七歳で異国人である高麗人と出会い、その予言を起点に権力への道を歩みはじめた光源 氏の物語を、東アジア世界からの<モノ・ヒト・情報>を手がかりに捉え直す。 『源氏物語』の古代東アジア世界に屹立するヒーローの物語として読み直す、野心的試 みの書である。

タイトル
地理学基礎シリーズ
著者
地理学基礎シリーズ1『地理学概論』:上野和彦・椿真智子・中村康子(編著)
地理学基礎シリーズ2『自然地理学概論:高橋日出男・小泉武栄(編著)
地理学基礎シリーズ3『地誌学概論』:矢ヶ崎典隆・加賀美雅弘・古田悦造(編著)
出版社
朝倉書店
ISBN
地理学基礎シリーズ1『地理学概論』:978-4-254-16816-7
地理学基礎シリーズ2『自然地理学概論』:978-4-254-16817-4
地理学基礎シリーズ3『地誌学概論』:978-4-254-16818-1
発行日
2007年4月25日
定価(税込)
3465円
内容
本シリーズ、『地理学概論』『自然地理学概論』『地誌学概論』は、地理学の全体像を具体的にわかりやすく解説することを目的とした教科書であり、大学における地理教育を体系的かつ効果的に実施するために編集されている。とくにこれから教員免許状を取得し、中学校・高等学校などで地理を教えようという人びとに向け、地理学の視点、概念、方法を平易に解説し、基礎的な学習ができるように工夫した。

タイトル
『魚のウロコのはなし』
著者
東京学芸大学准教授 吉冨友恭(著)
出版社
成山堂書店
ISBN
978-4-425-85261-1
発行日
2007年4月 8日
定価(税込)
1680 円
内容
【著者のことば】
(東京学芸大学 環境教育実践施設 准教授 吉冨友恭)
鱗(ウロコ)を知らない人はいないだろう。鱗は難しい最先端の科学用語と違って、老若男女おそらく世界中のみんながその存在を知っている。それにもかかわらず、本を検索しても「目から鱗の・・・」とタイトルの飾りに使われているものばかり。魚類学の専門書でもほんの数ページがあてられているにすぎない。
本書はこれまでにありそうでなかった鱗の専門書。魚類の歴史が私たち人類に比べてはるかに長いのと同様、鱗の歴史も長く、鱗一つをとりあげるだけでも様々なエピソードがある。本書では鱗を科学的な側面からだけでなく、歴史や文化、デザイン、料理、水族館の展示など、様々な側面から見ていきながら、鱗が私たちに語りかけてくるメッセージを体系立てて聞いていくことにしたい。
ふだんは注目されない薄っぺらい一枚の鱗に、実に多くの物語が隠されている。鱗は私たちが気づかない魚の様々な情報を提供してくれる上、私たちの日常生活の思わぬところで役立っていたりもする。まさに目から鱗だ。そんな話題を楽しみながら、みなさんにも鱗の面白さを再発見して頂ければ幸いである。


