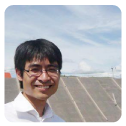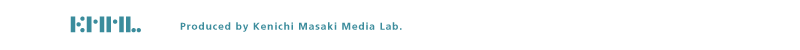男女がベッドの上で、ハートに火をつけるとき
いま私は大学の寮に暮らしている。大学寮というと私が思い出すのは、学生時代に、―あれは確か大学に入学したばかりの10代の頃のことであるが―友人を尋ねて訪れたある学生寮の光景だ。今も当時のままに現存するのかどうかは知らないが、とにかくその殺伐とした光景が鮮やかに蘇ってくる。もし、あの学生寮が改装もされずに存続しているのだとしたら、このように表現するのは評判を下げることになるので非常に心配ではあるが、正直に書くとすれば、あの寮は私が想像するところの刑務所の独房のような場所であった。ずっとあとに刑務所生活を経験したある漫画家の描いたコミックを読んだことがある。その描写を見て最初に思い出したのは、あの学生寮であった。その友人の部屋を訪れたときに内装を写真に撮った訳ではない。けれども、ドアの辺りには豹とかそういった獰猛な動物を入れておくための檻に取り付けられた柵のようなものがあったのが今も私の記憶の中に残っている。もう10年以上も前のことだから私の記憶にはひょっとするとバイアスがかかっているのかもしれないし、さすがに大学の学生寮の各部屋に柵が必要である訳がない。すると少しばかり記憶違いがあるのかもしれない。本当はもう少しまともな部屋だったのかもしれない。とにかく私の記憶の中には、陽も差さない薄暗い三畳か四畳ほどの檻のような場所に一人の友人が生きていた、というある意味ではショッキングな出来事としてそれは記録されている。靴底を床に叩き付けるようにして歩き近づく看守の足音がまるで聞こえてくるような、そんな寒々しい回廊に面した部屋が……。
そのような薄暗く鼠色の壁に囲まれた部屋に暮らすのは想像するだけで背筋が凍る思いだが、私はとても幸運なことに、もう少し清潔で明るい色に囲まれた部屋に暮らしている。窓を開ければ涼しい空気も入ってくる。隣の部屋と私の部屋を仕切る壁はそれほど厚くないようであるが、不満を言いにレセプションに行くほどではない。
私の部屋は他の部屋のほとんどがそうであるように、8人の学生が共同で使用するキッチンを囲んでいて、各部屋にそれぞれがひとりひとり暮らしている。音楽を好む学生の部屋からは、しばしばラップトップコンピュータのスピーカー特有の割れたような音が漏れている。ヘヴィーメタル・ミュージックが急激に大音量で再生されたときには腰を抜かしかけた。音楽は人によって好みも異なるし、何を聞こうが自由である。然は然りながら、私は隣人の迷惑にならぬよう、ヘッドフォンをコンピュータにプラグでつないで聞く。しかも、敢えて、ニュー・エイジとかクラシック・ミュージックの、そのなかでもとりわけもの静かなソロ・ピアノ曲ばかりを聞くようにしている。忘れることなくヘッドフォンをつけて。ウラジーミル・アシュケナージが奏でるモーツァルトをしみじみと聞くこともあるし、それまでほとんど聞くことのなかった、ジョージ・ウィンストンのようなポピュラーなものまでも最近は聴く。これなら騒々しさのあまり、誰かが怒鳴り込んでくることもないだろう。こうした二重の注意深さが私の特長なのだ。
ヘヴィーメタルの学生とは反対側に住む学生は、クラシック・ロックと呼ばれるような音楽を好むようで、1960年代のビートルズとかドアーズ、サイモン&ガーファンクルといった人気グループの曲をしばしば聞いているようだ。「Here comes the sun」とか、「Light my fire」、「I am a rock」といった曲である。フリートウッド・マックのような70年代の音楽も時折流れていることに気づく。彼はまた、同時にフットボール狂であるらしく、イングランド・プレミア・リーグを観戦している(らしい)。彼が部屋の中でどのように観戦しているのかは分からないが(ラジオなのか、テレビなのか、それともインターネットの中継を見ているのか)、エキサイティングなプレイに彼は鋭く反応し、また、ときにひどく落胆した声をあげることもあるので、私は観戦していなくても、その試合の進行がありありと想像できる。
かかと部分がもう完全にすり切れて失われてしまったような靴下のまま、彼はキッチンを物色し、何か食べ物を拵えたあと、それを器によそうような面倒なことはせずに鍋から食事する、というようないささかワイルドな青年である。地方から来ているそうで、訛りもあって何を話しているのかが分からないこともしばしばだが、愛嬌があって誰からも愛されそうな得難い笑顔を持っている。そして、それが故か、女子大生に大変な人気があるようで、様々な若く美しい女性を連れて歩いていたりする。そして、ときに―ここからが本題となる訳なのだが―彼の部屋にはそのうちの一人が時折訪れている(ように私は思う)。
ある、週末の夜遅く、皆が寝静まったような時間に、息を殺すようにしてひそひそと二人が会話しているのを私は耳にしたことがあった。断っておくが私は大学の課題を締め切りまでに完成させるために深夜までコンピュータのスクリーンに向かっていた。そしてそのとき偶然に、耳に取り付けていたヘッドフォンを外し、マウリツィオ・ポリーニの軽やかな鍵盤の音色が聞こえなくなった矢先のことで、その会話に聞き耳を立てて、或は壁に耳を当てていた訳では決してない。それはほとんどめったに起きることのない事故のようなものであった。彼らは甘い声でささやき合い(ひそひそと話していて、私にはその内容は全く分からない。)、やがて、成熟した愛し合う男女がベッドの上で行うとされる行為を、おもむろに始めてしまったようだった。彼らは周囲の部屋への最大限の配慮を施していたはずだが、それでもやむを得ず漏れる吐息の音やベッドの軋む音が、(彼らにとってはおそらく思いがけないことに)私の部屋の灯のもとにも届いていた。深夜の静けさは、昼間なら聞こえようのない小さな物音も、明瞭に伝えてしまう。私は思わず息を呑み、飛び出しそうになった目玉をやっとのことで元に戻しながら、絶対に物音を立ててはいけない、もし立てようものなら、彼らの幸せを台無しにしてしまう、というある意味では使命感のようなものを胸に、もう一度ヘッドフォンを装着し、そうだ、何かもっと激しい調子の音楽を聞こうと考えた。そうだ、そうならば、このようなときにはドアーズの「Light my fire(ハートに火をつけて)」しかない。私は私で、音楽によってハートに火をつけようとしたのだった。隣の部屋の彼らがそうしているように。「Light my fire」を10回ほど連続で聞いて、一段落ついたところで私はベッドに向かった。何度もあの印象的なオルガンによるメロディがこだました。静かな夜になっていた。今だから思うのだが、こういうときにこそ、私は二重の注意深さを発揮して、穏やかな曲を聴くべきだったのかもしれない。ヘッドフォンから音楽が漏れていたとしたら、元も子もない。うっかりものである。もちろん、それを彼らに確認するような馬鹿な真似もできない。
▼何だか学園ドラマでも始まりそうな感じですね。私は寮生活の経験がないので、こんなスリリングな経験はありませんが…異国の地で、桐山さんご自身もハートに火をつけるときがあるんでしょうかね^ ^