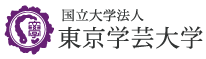2023年の年頭にあたって
あけましておめでとうございます。
2023年の年頭にあたり、ご挨拶いたします。
昨年、世間の耳目を集めた大きな教育問題に、学校のGIGAスクール化や、教員不足、教員の長時間労働等がありました。本学もこうした問題に必要な対応をとっているところですが、一方、本学が、これから、全学的な資源を注力して取り組む独自の課題に、昨年3月に文科大臣から指定を受けた教員養成フラッグシップ大学としての事業があります。
本学は、この事業遂行のためのエンジンとなる組織として、先端教育人材育成推進機構を立ちあげました。機構は、先導的な学生教育プログラムの研究開発、成果の普及展開、教職課程に関する制度改善の提言を行うことにしており、その機能を担うために8つのユニットとリエゾン・チームを置きました。それらの組織を整備し、新しいカリキュラムに対応できる人事計画も立てて、全学的な承認も得ました。すでに、各ユニットは、打ち合わせ・会議を重ね、シンポジウム開催などの活動を活発に行っています。リエゾン・チームは、既に20に近い教育委員会や大学と新たな連携協力関係を構築し、今現在もさらなる体制拡充を図っています。
この事業は、本学の第5期の中期目標・中期計画期間の中心となる取組であり、さらに、"有為の教育者養成"という使命に沿った本学の将来の形・方向を決めて行くものと、私は思っています。こうした意味で、この教員養成フラッグシップ大学の事業は、上で申し上げたように、本学が、有する資源を注力して取り組むべき重要な課題であると思っており、教職員協力して進めていきたいと思います。
また、今年は、本学の礎が創られてから150年となります("創基150周年"と言っております。この"創基"という聞きれない言葉の意味については、本学ウェブサイトをご覧いただけますと幸いです)。年史の出版等の行事も準備しております。年末年始のお休みには、年史の序文を書くことに費やしました。年頭から恐縮ですが、周年事業のためにご寄附など賜りますと幸甚です。
コロナ禍となって、3回目の新年となりました。新型コロナ・ウィルスの感染は収まっておりませんが、われわれの社会は、経済活動を優先するという選択をしました。本格的なウィズ・コロナ時代を迎えることになるわけですが、本学は、コロナ初年から、学生教育を途切れることなく、継続することができています。つねに感染の広がりに注意を払い、自ら罹患しないよう十分に気をつけながら、これまでの経験を活かし、教職員力を合わせ、わが国を代表する教員養成系大学として、"有為の教育者養成"という使命を、引き続き粛々と果たしていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。引き続きのご支援・ご協力をお願いいたします。