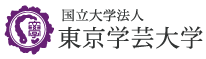ダイバーシティ・インクルージョン・フォーラム(と病院ラジオ)
本学のダイバーシティ・インクルージョン推進本部が主催するダイバーシティ・インクルージョン・フォーラムが、2月12日(木)に開催されました。今回のテーマは「『生きる』を創るがん教育~当事者視点で考える、いのち、学校、がん教育~」というもので、がん教育の普及に会社として取り組まれているアフラック生命保険株式会社から4人の社員の方がいらして、お話しくださいました。いらした4人の方のうち、お1人は入社後にがんを経験され、もうお1人は小児がんの経験者ということでした。そうした社員の方が、がん教育の普及に当たられているのでした。
私は、次の予定があり、肝心の当事者の方のお話は聞くことができず、アフラック社のダイバーシティの取り組みを、女性のダイバーシティ推進部長の方から伺ったところで中座する仕儀となりました。そこでは、日本では女性の管理職・役員への登用が他国に比べて大きく遅れているということから、女性の管理職登用ということに主たる焦点をあててお話しいただきました。
印象深かったことを簡単にまとめますと、アフラック社は、創業時から入社後の役割期待・教育・評価に男女差は設けておらず、女性活躍が当たり前の風土だったそうです。1997年には生命保険業界初の女性役員を登用、1998年には営業現場に女性支社長が2名誕生と実績を上げてきましたが、2014年、女性管理職比率の企業平均との差が縮小してきたということに気づき、KPI1として「2020年末までに、指導的立場に占める女性社員割合を30%以上にする」、およびKPI2として「2025年末までに、ライン長ポストに占める女性割合を30%以上にする」をかかげました。さらに、経営トップのコミットメントが大事と考え、2015年からは定期的に日米の経営陣からダイバーシティ推進の意義を伝えるカンファレンスやシンポジウムを開催した結果、KPI1は1年前倒しで達成、KPI2も2025年末に達成できたと言います。また、男性育休取得の取得率は2019年以降、7年連続100%を維持しているということで、これには、他にも増して驚きました。
最後に、「女性管理職登用を妨げている要因に、女性自身が管理職になりたがらないことがある。その理由を問うと、『プライベートな時間がなくなる』と言われることが多いけれども、そんなことはない。その証拠に、自分は週に2日は勤務後に専門学校に通い、中小企業診断士の資格取得を目指している。そうした自分の時間を確保できているということを身をもって示している」とお話しされたことが、非常に印象的でした。最初の自己紹介の時に、中小企業診断士の資格取得に向けて勉強中とおっしゃっていたのですが、なぜそんなことをおっしゃるのかと思わないでもなかったのですが、それはここと結びついていたのかと得心しました。
本学は、村松学長時代に男女共同参画推進本部を立ち上げ、補助金も得て多くの取り組みを進め、先進的だと東京都から表彰もされるほどだったのですが、気がつけば、それらはみな当たり前のこととなってしまい、ダイバーシティ・インクルージョンという点からは、他の後塵を拝しているような状態になっていました。この辺りは、アフラック社が、他社との女性管理職比率の差が縮小してきたことに気づいたというのと同じような状態で、そのため、2年前に、竹鼻ゆかり副学長を本部長とするダイバーシティ・インクルージョン推進本部を立ち上げ、気持ちを入れ替えて新たな取り組みを進めてきました。アフラック社のようには行きませんでしたが、世に先んじた取り組みを行う体制は整えたかと思います。今後に続いていければと思います。
余談:
2月11日の朝にテレビをつけたところ、サンドウィッチマンの"病院ラジオ"が、埼玉のがん専門病院を舞台にして放送されていました。病院ラジオというのは、病院に一日だけラジオ局を開き、患者や家族の方のお話をサンドウィッチマンのお2人が聞くという、NHKの番組です。私はサンドウィッチマンと同じ仙台の出身なので、彼らの番組は好んで見ることが多く、この番組もそのひとつなのですが、この日見ることになったのは(翌日にフォーラムがあるから、と考えたわけではなく)まったくの偶然でした。ただ、この番組は、見ていると泣けてくることが多く、なので、見たいような見たくないような...という番組でもあって、11日も泣けてきて困りました。番組には4人のがん患者の方が登場して、これまでの経過や現在の病状などをお話しになっていました。この番組でいつも思うことは、人間には本当に様々な病気があり、様々に苦しんでおられる方がいるということです。今回も、がんはよく知られている病気のようにも思うのですが、こんながんもあるのかと認識させられました。また、これもいつも思うことですが、出てこられる患者の皆さんが、病状は決して軽くないのに前向きに生きてらっしゃること、そして、それには、医師や看護師などの医療関係のみなさんの他、特にご家族の理解と支援、励ましが常に伴っているということで、今回もまた強く感銘を受けました。
しかし、それにしてもよくもこうした番組を考えたものだと思います。そして、この番組は、サンドウィッチマンのお2人の人柄のよさ、伊達さんの仕切りと冨澤さんの受けというコンビネーションがあってはじめて成立する番組だとも思います。このお2人は、東日本大震災に見舞われた故郷・仙台をはじめとする東北地方の復興支援をずっとされていると聞きます。
ちなみに、お2人の母校である仙台商業高校(略して、仙商)は、東北大学旧教養部の丘陵を東に下って通りを挟んだ向かい側にあり、私が所属していた東北大の柔道部は、いつも練習している教養部の柔道場が使えない時には、仙商の道場を借りて練習していました。サンドウィッチマンのお2人はラグビー部だったようですが、その頃の仙商は野球で有名な強豪校として鳴らしており、甲子園にも何度か出ていました。柔道も弱くはなく、仙商校生と組むこともありましたが、よい選手でした。
そうしたことも、私がこのお2人に親しみを感じる理由になっていると思います。仙商は、私が学生の頃(そして、サンドウィッチマンのお2人が在籍されていた頃)は男子校でしたが、今は共学となり、仙台市北部に移転しました。そして、その跡地は、隣に地下鉄の駅ができたこともあり、きれいに整地され、観光客向けのひろびろとした駐車場となっています。