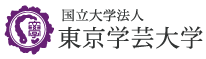「アート・アスレチック教育センター」
11月13日の水曜日、今年新設した本学アート・アスレチック教育センターのオープニング・イベントがありました。記念講演に、本学出身でパリオリンピックで、女子48kg級で金メダル、団体戦で銀メダルを獲得した角田夏実さんをお呼びして、「準備力」と題してお話し頂きました。また、本学2人目の栄誉教授称号を授与いたしました(お一人目は、栗山英樹WBC優勝監督)。大変盛況で、本学芸術館が一杯となりました。その時イベントの冒頭にしたご挨拶を掲載します。アート・アスレチック教育センターを、お見知りおき頂ければ幸いです。
――――――イベントでの挨拶――――――
本日は、アート・アスレチック教育センターのオープニング・セレモニーに多数のみなさまにご参加いただき、まことにありがとうございます。学長の國分でございます。日ごろから、ご支援頂いております団体や個人の皆様、並びに小金井市・国分寺市・小平市にお住まいの皆様にもご臨席を賜りました。心より深く御礼申し上げます。
さて、本学の名称である東京学芸大学の「学芸」という言葉は、「学問」と「芸術」諸般を表しており、本学の教育と研究において「芸術」と「スポーツ」はなくてはならないものです。そして、スポーツ、芸術の教育やそれぞれの専門で活躍する人材を数多く輩出して参りました。最近のことで申しますと、記憶に新しいパリオリンピックの女子柔道で、本学の卒業生である角田夏実さんが、抜群の強さで金メダルを獲得いたしましたし、また昨年度はワールド・ベースボール・クラシックの日本代表監督として、同じく本学の卒業生である栗山英樹さんが、チームを世界一に導きました。角田夏実さんには、後ほど、栄誉教授称号授与式とご講演をいただきます。
芸術とスポーツが、人生を豊かにすることは言うまでもありませんが、教育界では、現在、理数系人材の必要性から、理数系教育に重点がおかれるような動きが進んでおります。しかし、そうした中では、いっそう、芸術やスポーツに対する理解の必要性が増しています。Science、Technology、Engineering、MathematicsからなるSTEM教育より、ArtのAを入れたSTEAM教育が、最近では、よく言われるというようなことなども、そうしたことの現れかと思います。また、ウェル・ビーイングを重視する人の生き方からは、学ぶことが、何かを達成するための手段というのではなく、学ぶこと自体が楽しい、また、楽しみながら学ぶことができるということが重要で、芸術やスポーツは、そうした観点から注目されているところです。
本学では、こうしたコンセプトに基づき、そうした芸術・スポーツの研究開発、地域貢献を行うことのできるセンターを構想し、文部科学省に働きかけてきましたが、本年度から「アート・アスレチック教育センター」としての設置が認められました。こうしたセンターは、本学独自で非常にユニークな、先進的で、全国に類を見ないものでございます。
今後、こうしたコンセプトを体現すべく、特に、本学の芸術とスポーツの活動が、地域や社会に一層貢献できるよう、本センターを運営して参りたく存じます。みなさま方におかれましては、今後とも引き続きのご支援・ご協力をお願いしたしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。これをもちまして、開会のご挨拶とさせていただきます。以上です。ありがとうございました。
―――――――――――――――――――
柔道家・角田夏実氏が東京学芸大学から栄誉教授称号を授与され講演会を実施 | 国立大学法人東京学芸大学のプレスリリース
栄誉教授称号授与の様子【左:学生 中央:角田選手 右:國分学長】
栄誉教授称号授与の様子【角田選手】
本学正門通りバナーでの撮影【左:角田選手 右:國分学長】