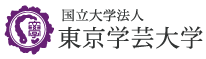あんぱん(1)
以前の学長室だよりで、NHKの朝の連続ドラマ「あんぱん」を見ていることを書きました。これは、「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さんのご夫婦をモデルとしたもので(タカシとノブ)、このお二人にとって、第二次世界大戦と終戦後の体験は、その後の人生に大きく影響したものとなっています。NHKの朝ドラでの戦争の描き方については、感銘を受けるものであることを以前にも記しましたが、今回のそれは、これまでにも増して、強く印象に残るものでした。
6月最後の2週間は、専ら召集されたタカシの軍隊での生活及び中国での転戦が描かれました。たびたび古参兵に殴られるタカシ。幼馴染のイワオは、自分を慕ってるのだと思っていた中国人の子どもに銃で撃たれて亡くなります。実は、子どもはイワオに両親の命を奪われており、復讐の機会を狙っていたのでした。イワオはうすうすそのことに気づいていて、これでいいんだと言って息を引きとります。この件にまつわって、度々たかしを救うクールで、謎めいた(妻夫木聡さん演じる)八木上等兵の感情の爆発と慟哭。また、飢えに苦しめられて、民家に押し入り、老婆に銃を突き付けて、卵を奪い、ゆでられた卵を殻ごとむさぼり食うタカシら日本兵。老婆は「飢えは人を変える」と言います。いつもはこの番組をみるのが楽しみでしたが、この2週間は、見るのがつらくなりました。
そして、タカシは、海軍に入った自慢の弟の千尋をこの戦争で亡くします。こうした経験は実話で、やなせたかしさんが、しばしば語っていた「僕は戦争が大嫌い」という強い反戦思想を抱かせることになったと言います。
タカシも苦しんだ戦場の飢え......一橋大学名誉教授の吉田裕先生の本(『日本軍兵士』、『続・日本軍兵士』いずれも中公新書)によれば、日中戦争以降の第二次世界大戦での日本軍兵士の戦没者数は、230万人で、その中の餓死者の占める割合としては、37%と61%という、従来の研究者の2つの推定値をあげています。戦死とされた兵士が戦闘で死んでいないとは!そして、餓死者の割合がこんなに高いとは!南方の戦線で日本兵が飢えに苦しんだということは知っていましたが、そうしたことが例外的なことではないことを知り、その割合に愕然としました。低い方でも3分の1強です。ネットで、吉田先生が戦争研究について話している記事があり、その中で、無残な死を遂げた兵士たちのありようについて「知れば知るほど絶望的な気持ちとなる」、「研究の過程では、胸が締めつけられる思いを何度もしました」と話されていましたが、まったく同感です。戦闘で亡くなるのではなく、異国の地で飢えて亡くなるとは...。これは、陸軍が兵たんを軽視し、食料補給を十分考えていなかったためだと言います。現地で調達する、「現地自活」(=略奪)という言葉まであり、それが勧められ、手引きも作られていたというのだから、唖然とします。
(この項続く)